株式会社ヨーカ堂を設立
洋品店時代の羊華堂の経営
1920年4月(大正9年)に吉川敏雄氏が浅草で洋品店「羊華堂」を創業。戦時中の1940年4月に暖簾分けによって伊藤譲氏が独立した。1945年の戦災によって店舗が焼失したことを受けて、1946年に店舗を北千住に移設した。この経緯から、終戦直後のヨーカ堂は北千住を基盤として小売業を展開した。
伊藤雅俊氏によるスーパーへの進出
1956年に伊藤譲氏が逝去したことを受けて、伊藤雅俊氏(イトーヨーカ堂・創業者)が事業を継承。欧米視察を通じてスーパーマーケットの将来性に着眼した。そこで、従来の小売業の形態を改めてスーパーマーケットによる大量販売を志向するために、1958年に株式会社ヨーカ堂を設立した。
北千住を軸にスーパーを多店舗展開
ヨーカ堂の設立とともに、伊藤雅俊氏は北千住の店舗の増築を実施。総合スーパーを志向することで、日用品・医薬品・化粧品・加工商品などの様々な商品を扱う小売業として販売を拡大した。
1961年には赤羽店を新設して関東圏を中心に多店舗展開を開始。多店舗展開によって大量仕入れを実現することで、安く商品を販売する体制を構築。1972年2月末時点で27店舗を展開した。地域別売上高は、東京都内が58%・埼玉県19%・千葉県11%であり、東京(北部)および埼玉県での店舗展開が中心であり、ドミナント展開を志向した。
1972年2月時点における売上高は477億円であり、1店舗あたりの売上高は9億円前後。いずれの店舗も大型店を志向することで、店舗の運営効率の向上を図った。商品別の売上構成比では、衣料品48%、食料品28%であり、普段着の販売が売上を支えた。販売品目は約10万店であり、満遍なく商品を販売した。
国内スーパーで売上高10位を確保
1972年2月期にイトーヨーカ堂は売上高477億円・当期利益7.4億円を達成。業績好調を受けて、1972年9月に東京証券取引所第2部に株式上場した。ただし、1972年度におけるスーパー業界の売上高ランキングにおいて、イトーヨーカ堂は10位の地位であった。
競争面においては、関東圏では西友、イトーヨーカ堂の2社が大手スーパーとして認知されたが、同時期にダイエーの関東進出が本格化するなど、スーパーマーケットを巡って熾烈な出店競争が発生していた。
なお、1970年前後にはスーパーの大量出店によって進出先の商店街が反発するなど、スーパーに対する大量出店に対する社会的な批判も強まりつつあった。このため、1970年代以降のスーパーの出店競争については、政治的な制約を伴うこととなった。
日本の小売業がアメリカと同じ道をたどるとはいえないが、現在、アメリカの方向に向かっていることは事実である。(略)私は昭和30年当時、まだ1店も出店していない時(注:北千住店のみで運営)に、1回アメリカに行った経験だけで、銀行の重役を集めてチェーン・ストアの話をし、融資を受けた。まさに「盲蛇に怖じず」である。
イトーヨーカ堂が東証第2部に株式上場
米デニーズと業務提携・レストラン事業に参入
ヨークベニマルと業務提携
米セブンイレブンと業務提携
先日、アメリカのセブン・イレブンのコンビニエンス・ストアの伸びを見たてみたら、昭和30年〜40年の間に500店から5,000店に伸びている。今の日本でのコンビニエンス・ストアはアメリカに約20年遅れている。またレストラン業も非常に注目されるところだが、これもアメリカからは20年遅れている。
セブンイレブン1号店を豊洲に開業
山本茂商店が加盟に申し込み
1973年11月にイトーヨーカ堂のセブンイレブン係宛に、山本茂商店からFCの加盟に関する問い合わせが手紙であった。差出人は、山本憲司氏(当時24歳)であり、東京都江東区豊洲4-6-1で酒屋として「山本茂商店」を経営する2代目であった。セブンイレブンは日本国内における加盟店を募集していなかったが、山本氏は業界雑誌を通じて米国のセブンイレブンを知っていた。そこへ、イトーヨーカ堂が米セブンイレブンと提携したことを日経流通新聞の記事を通じて知り、自らフランチャイズへの加盟を申し出た。
日本国内のセブンイレブンでは、コンビニ出店にあたっての政策がまだ未決定の段階であった。そこで、1973年12月に岩国修一氏(セブンイレブン・取締役)は山本憲司氏を訪ねて、まだFCは計画段階であることを伝えた。だが、山本憲司氏はセブンイレブンの業態に転換することを望んでいた。最終的に1974年1月にセブンイレブンは、山本憲司氏の熱意を買い、山本茂商店をセブンイレブンの1号店として加盟することを認めた。
なお、山本茂商店は元々酒屋であり、酒類販売が可能なコンビニとして開業できた点で、品揃えの面で優位だったことも、1号店に選定された理由の一つであった。ただし、山本茂商店が存在する立地は豊洲であり、多少の団地が存在したものの、当時は工場が集積する地区であった。
セブンイレブン1号店の開業
1974年5月15日午前7時に東京都江東区豊洲にて、旧山本茂商店を改装する形で、セブンイレブン1号店(25坪)を開業。日本国内における1号店としてオープンした。1号店について、直営店ではなくフランチャイズを採用した理由は、難易度の高いFCで事業を軌道に乗せれば、ノウハウが蓄積されやすいと判断したことにあった。
セブンイレブンとしては、1号店の山本茂商店に対して、酒屋店時代の粗利額の最低保証、セブンイレブンの撤退時は復元および補償の実施を約束したという。
5年間で500店舗を展開
セブンイレブン1号店において、年商1.5億円を予想したが、実際には年商1.8億円を記録。立地条件が悪い中で売上を確保したことで、セブンイレブン1号店の滑り出しに注目が集まった。このため、各地からセブンイレブンへの加盟の問い合わせが相次いだ他という。
1974年からセブンイレブンは物流効率化のために、ドミナント展開による多店舗出店を本格化。酒販店および食料品店について、FC契約により、関東の特定地域における集中出店を志向した。
この結果、1978年度までに関東圏を中心に国内591店舗のセブンイレブンを出店した。国内セブンイレブンにおいて売上高725億円を確保し、コンビニ業態で業容を拡大した。
| 年度 | 売上高 | 店舗数 | 備考 |
| FY1974 | 7億円 | 15店 | 1号店を開業(豊洲) |
| FY1975 | 48億円 | 69店 | |
| FY1976 | 174億円 | 199店 | |
| FY1977 | 398億円 | 375店 | |
| FY1978 | 725億円 | 591店 |
(注:セブンイレブン宛の手紙の要旨)私は江東区豊洲で酒屋をやっているものですが、これからセブンイレブンのコンビニエンスストアをやりたいと思います。私と私の家族は商売好きです。果たしてやれるかやれないか、わかりませんが、セブンイレブンがフランチャイズチェーンをおやりになるということでしたら、せひ資料を送ってください
セブンイレブンが東証2部に株式上場
ヨーカ堂グループでPOS導入を開始
米セブンイレブンに資本参加
セブンイレブン1万店舗を突破
セブン&アイを設立(経営統合)
7-Elevent, Inc.を完全子会社化(TOB)
ミレニアムリテイリングを買収(そごう・西武百貨店)
ヨークベニマルを完全子会社化
レストラン事業を1社に集約
セブンイレブン3万店舗を突破
セブン&アイ・フィナンシャル・グループを設立
百貨店事業を統合
ニッセンHDを買収(TOB)
鈴木敏文氏がCEO退任
米Speedwayを買収
北米におけるコンビニおよびガソリン給油事業を強化するため、Speedwayブランドを展開するSpeedway LLCの買収を決断。株式100%の取得で完全子会社化し、取得価額は2.3兆円。セブン&アイは、買収による「のれん」として1.3兆円を計上した。セブン&アイHDとして2兆円を超える大型買収となった。
Speedwayの買収によって、北米におけるコンビニブランドは「7-Eleven」と「Speedway」の2つを展開する形となった。買収によって商品の相互供給などにより、販売拡大を目指す計画。
バリューアクトが社長退陣を提案
バリューアクトによる株主提案
2020年11月からバリューアクトは、セブン&アイHDとの対話を開始。2023年までに約30回に及ぶ意見交換を実施した。セブン&アイHDとしては、2021年12月の取締役会においてバリューアクトと対話する場を設けるなどして対応した。
この過程でバリューアクトはセブン&アイHDにおける不採算事業(スーパーストアおよび百貨店)の存在を問題視。2022年5月にはセブン&アイHDに関する経営上の問題点を指摘した資料(スライド75枚)を公表するなど、公開討論の形で経営改善を要求するに至った。
ところが、セブン&アイHDの経営陣はバリューアクトの提案を否定。バリューアクトの行動について「同社が関心を有するのは、堅実な価値創造を犠牲にした上での短期的な株価上昇だけであるということです」(2023/4/25:セブン&アイHD開示)として否定。この結果、セブン&アイHDの経営陣とバリューアクトは対立するに至った。
バリューアクトによる退陣要求
セブン&アイの大株主である米系ファンド(バリューアクト)は、株主提案を通じて井坂社長を含めた4名の取締役の退陣を要求した。
バリューアクトは、セブン&アイHDにおいて、収益性の低いスーパーストア(旧イトーヨーカ堂)や百貨店(旧そごう・西武)事業を継続していることを問題視し、高収益のコンビニ事業(セブンイレブン)に集中することで企業価値が向上すると判断していた。ところが、セブン&アイHDの経営陣は不採算事業からの撤退を決断できず、時間が経過していた。
このため、バリューアクトはコンビニ事業への集中に踏み切れないセブン&アイの経営陣に対して、退陣を要求した。
井坂社長の続投
2023年5月のセブン&アイHDの定時株主総会において、井坂社長の取締役選任が決定。賛成比率は76.36%であり低水準での社長続投が決定した。なお、株主提案による取締役4名の選任については賛成比率30%台により否決された。
この結果、セブン&アイの取締役については、会社提案が通過する形となった。
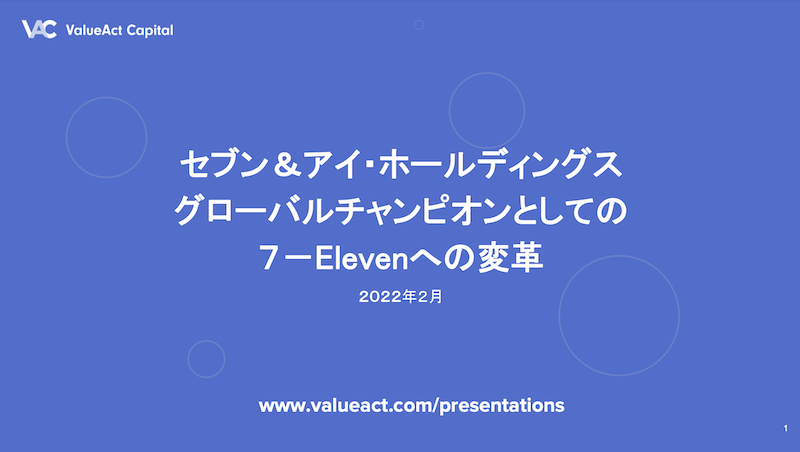
そごう・西武を事業売却
セブン&アイは不採算事業である百貨店(株式会社そごう・西武)事業の売却を決定。