株式会社丸井を設立
のれん分けにより創業
丸井の創業経営は複雑な過程を経て、1935年に株式会社丸井の設立に至った。この理由は「のれん分け」による独立を志向したことと、親元にあたる「丸二商会」からの嫉妬にあった。
1931年2月丸井の創業者である青井忠治氏(当時27歳・富山県出身)は、勤務先であった月賦販売商・丸二商会の中野店(東京都・中野駅前)を買い取る形で独立を果たした。なお、月賦業界は儲かる商売として知られ、当時の大卒の初任給が60円だったのに対し、青井忠治氏は1.1万円の貯金(現在換算3600万円)を蓄えており、これが創業資金となった。
中央線沿線で多店舗展開
創業時点で青井忠治氏は主力商品であった家具に注力して「日本一」の月賦店を志向。中小企業にとどまらない事業展開を志向し、丸二商会・中野店として順調に業容を拡大した。
1935年には阿佐ヶ谷店を新設して中央線沿線に店舗網を拡大。特定路線の沿線に店舗を構えることで、集金業務の効率化を実現した。このため、創業期の丸井の店舗網は中央線沿線に集中している。
株式会社丸井の設立(商号変更)
ところが、親元にあたる「丸二商会」は、競合の出現を警戒。丸二商会は青井忠治氏に対しては商号を「丸二」から変更するように要請した。このため、青井忠治氏は商号を「丸井」に変更。1937年に株式会社丸井を発足し、丸二商会から完全に独立を果たした。
中国人が中野店を不法占拠
第二次世界大戦中に丸井の中野本店は休業していたが、終戦直後に中国人の王氏によってある日突然不法占拠され、中華料理屋兼結婚式場に様変わりした。これに対して、丸井の創業者・青井忠治は返還交渉を開始。終戦直後は中国人に対して日本人の立場は弱く、交渉は命がけであったが、青井忠治は粘り強く交渉を継続する。
交渉を経て、1947年までに青井忠治は中国人に対する立ち退き要求に成功。だが、不法占拠した中国人は現在換算1億円を要求したため、青井忠治は自らの自宅(杉並区和田本町)を売却して、中野店を取り戻した。
店舗専用のクレジットカードを発行
1952年に丸井の創業者・青井忠治は渡米し、現地でコンピューターを活用したクレジットカードが普及している事実に驚愕。以後、青井忠治は丸井におけるクレジットカードの導入を模索する。
そして、1960年に店舗専用のクレジットカードを導入した。発行初年度に5万枚のカードを発行し、うち30%が丸井の店舗に来店してカードを作成した。なお、日本初のクレジットカードの発行とされることもあるが、クレジットカードの定義が曖昧なため、断言しづらい面もある。
小規模店舗を閉鎖し、都心部に大型店を出店
店舗の大型化に積極投資
1960年代を通じて、丸井は小規模の月賦専門店における都配合を実施。東京都心部の主要駅前に大型店を出店することで「百貨店」に業態を近づける方針を決断して「月賦業界の三越」を目指す。1966年から1971年にかけて丸井は10店舗を閉鎖し、代わりに大型店の出店を最重要課題に据えることで、スクラップアンドビルドを急いだ。
新宿進出を決断
丸井は店舗大型化を本格化させるために新宿進出を決断。当時、丸井の資本金が3.6億円出会ったのに対して、4億円を投資して新宿店(のちの新宿店ヤング館)を開業した。それまで丸井の最大の店舗だった吉祥寺店の2倍の店舗面積であり、丸井の旗艦店となる。社運をかけた投資について、青井忠治は「今後の当社の命運を決するものでありまして、誠に責任の重大さを痛感しています」と述べている。
月賦業界で国内トップへ
1960年代まで月賦百貨店No.1の売上高を誇ったのは緑屋(現クレディセゾン)であったが、都心部を中心に大型店を出店した丸井が徐々に追い上げ、1970年には緑屋の売り上げを凌駕。月賦百貨店では丸井がNo.1の地位を確保する。
東京証券取引所第2部に株式上場
店舗大型化のための積極投資を受けて、株式上場による資金調達を決定。1963年に東京証券取引所第2部に株式上場を果たした。
青井忠雄が社長就任
同族経営を志向
1972年に青井忠雄氏(当時39歳)が丸井の代表取締役社長に就任。2005年に社長を退任するまで約33年にわたって丸井の経営トップを担った。なお、青井忠雄氏の社長就任をもって、創業者の青井忠治は社長を退任し、1975年に71歳で逝去している。
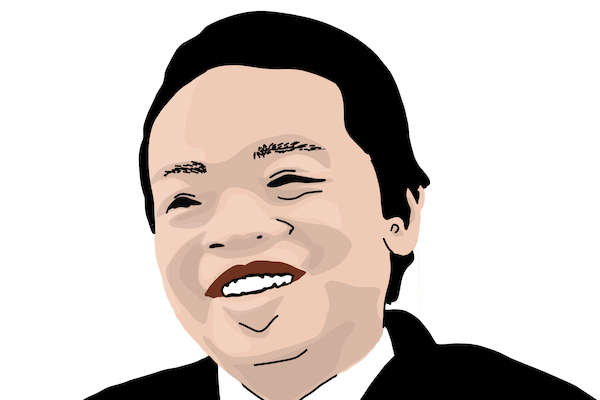
新宿三丁目・日活帝都座跡地を買収
丸井は新宿での店舗をさらに充実するために、1973年に伊勢丹新宿本店の真向かいに存在した日活帝都座跡地を47億円で買収する。土地の買収交渉にあたっては、青井忠治が戸田建設(キーマン)に対して毎日電話をかけるなど、土地取得に対して尋常ではないほどの熱意をかけていた。
クレジットカードの店舗即時発行を開始
システム投資を積極化
丸井はクレジットカードの発行スピードを向上させるためにオンライン信用照会システムを稼働。クレジットカードの発行コストの低下を目論む。なお、店舗向けにIBM3650、コンピューターセンタにIBM370を導入し、顧客の収入や支払い状況を即時に把握できた。
クレジットカードの即時発行を実現
丸井はクレジットカードの収益を増大させるために、クレジットカードの店舗即時発行を開始。主に若者をターゲットにクレジットカードを発行することで、金融収入を確保する。
26期連続で増収増益
1987年に丸井は26年連続増収増益を達成。新宿や池袋など、東京都心部に出店することによって若者顧客を獲得し、クレジットカードの会員として誘導。販売面では、DCブランド(イッセイミヤケなど、デザイナーズ・ブランド)などの高額商品によって若者のニーズ(クレジットカードによる分割払い)に応え、高収益を確保する。
取扱商品をヤング向けファッション中心に転換
家電・紳士服の偏重から脱却
1960年代を通じて丸井の主力商品は、紳士服や家具であり、若者(女性含む)向けのファッションの取り扱いは限定的だった。1966年1月期における商品別の取扱高の比率は、紳士服22.6%、家具19.1%、家電・時計・カメラ19.1%、婦人子供服13.4%、その他25.5%であった。
そこで、1970年代を通じて丸井は20代の「ヤング」をターゲットに品揃えを転換。ニーズが高い女性向けファッションを充実させる方向に舵を切り、1980年代には国内でブームとなったDCブランドの取り扱いを積極化した。
この結果、1980年代を通じて丸井はファッションに興味がある若者を中心に集客に成功。1987年度における商品別の売上構成比率は、女性向けアパレル28.4%、男性向けアパレル22.9%、家電・楽器11.1%、家具8.7%であり、若者向けアパレルに偏重する商品構成となった。
特に、若者向けにブームとなったDCブランドの拡大が焦点となった。単価が数万円〜10万円以上と高額なため、丸井が展開する分割払いや、キャッシングとの相性が良く、結果として1980年代を通じて丸井が増収増益を達成した原動力となった。1987年度には売上高におけるDCブランドの比率が13.5%に達し、DCブランドだけで1066億円(FY1984時点のDCブランド売上は310億円)の売上を計上。DCブランドの売上拡大が、丸井の増収増益を支えた。
キャッシングに新規参入
キャッシング(ローン)に参入
クレジットカードによる収益源を多様化するために、貸金業(キャッシング)に新規参入。専用の無人機を介して若者向けのキャッシングを拡大し、1987年に貸付残高800億円を突破。小額の貸し付けが中心であり、貸倒率は低かったと言われている。
ローン収入が粗利貢献
2000年代前半における丸井は売り上げ成長に苦戦した一方で、収益面では消費者ローンによる利息収入が業績に貢献。改正貸金業法の施行前にあたる2005年度には、年間粗利653億円を計上しており、丸井における重要な収益源となった。
ただし、消費者ローンの事業展開に際して、丸井はグレーゾーン金利である27%前後の金利を採用しており、のちに利息返還として莫大な損失を計上する布石となった。
PL(損益計算書)をよくしようと、いろいろ無理をしたわけです。クレジットカードはもともと丸井のお買い物をしやすくする分割払いを主たるビジネスにしていましたが、利益を上げるためにキャッシングを始めて貸し付けを増やしていきました。
ころが、2006年の貸金業法改正前に、いわゆるグレーゾーン金利の議論が出ましたよね。出資法と利息制限法の上限金利間の約10%の金利差が違法なのではないかということになり、一気に財務が悪化しました。当時、キャッシングの残高が2500億円ありましたから、10%金利が下がると、毎年250億円の利益が永久に消滅するわけですよね。当時の営業利益約450億円なんて、半分以下になってしまう。加えて、過払い返金請求が数百億円規模でありました。
減収決算により連続増収増益がストップ。業績低迷へ
1993年1月期に丸井は前年の売上高6014億円に対して、売上高5760億円の減収決算を計上。バブル崩壊によって若者による高級品に対する消費が低迷し、小売業界では無印良品やユニクロといった「安くて品質の良いもの」を扱う業態が支持される時代が到来し、丸井の順調な急成長は幕を閉じた。
当時の丸井の経営陣は事態を深刻に捉え、1991年から「営業会議」による議論を開始。毎週15:00〜22:00にわたって対策を議論したものの、有効な施策を打ち出すことはできず、業績低迷が続いた。
僕が営業を担当する取締役だった時のことです。毎週、午後3時から夜10時まで夕食もとらずに行われる「営業会議」というものがありました。バブル崩壊後の91年ごろから始まったもので、急落した業績をどうすれば回復させられるかと、「ここは正念場だ」と責任者たちが一堂に会して時間も構わず議論をしていたのです。
当初は、数年努力すれば業績は回復するだろうと考えていました。しかし、回復どころかどんどん悪化していったのです。そのまま5~6年が経過し、僕だけではなく、周囲の責任者たちも限界に近づいていました。
そんなある日、いつもの営業会議で、食事もとらず頭がもうろうとしている時、はっと気が付いたのです。「いつも同じおじさんたちばかり集まって、延々と意味のない議論をしていること自体が、業績が回復しない最大の原因なのではないか」と。
大型店舗への投資を継続
大型店舗への投資を継続。2003年には神戸(三宮)に進出して関西進出を実施。翌2004年には大型店舗として北千住マルイを新設した。北千住マルイは、丸井のなかで最大規模の店舗であり、2020年3月期の北千住店の売上高は389億円(丸井の店舗No.1)であった。
組織制度改革を実施(失敗)
希望退職者の募集・組織改革を実施
2003年8月に丸井は大規模な組織再編を発表。社員数の5%に相当する700名の希望退職者の募集と、社員数の95%にあたる5500名の子会社への転籍を発表した。希望退職者に対しては割増退職金の支給(最高額2000万円)を決定し、固定費削減を本格化した。
加えて、実力主義による評価制度を開始し、評価サイクルを半年から3ヶ月毎に短期化。報酬体系についても成果主義に基づく仕組みを導入し、基本給を削減しつつ成果報酬の配分を増加させた。給与が下がる社員に対しては5年間に限って差額を補填する制度とした。
これらの改革の背景思想としては、社員一人ひとりの専門能力を生かすことによって、業績改善に結びつける意図があった。
人事給与システムの更新
組織改革にあたって、丸井は約100億円を投資して人事給与システム(ERP)の刷新を実施。ベンダーに東芝ソリューションを選定し、基幹システムの再構築を同時並行で推進した。システム稼働後は、グループ各社の人事情報の管理・給与計算が一元化された(出所:東芝ソリューション案内冊子)。
社員と経営陣の信頼関係が悪化
制度改革の結果は「惨憺たる結果」(2019/2/21nikkei style)に終わり、従業員と会社の信頼関係が低下したという。このため、丸井は成果主義の導入を廃止するに至った。
赤字の直接の要因は外部環境の変化ですが、それ以前からの内部の問題が相当深刻でした。やたらと組織や人をこねくり回して、それでも苦しいから03年に抜本的な制度改正に踏み切って成果主義を導入したり、販売の社員を別会社に転籍させたりしたのですが、これがもう惨憺(さんたん)たる結果で
eコマースに本格参入
青井浩氏が代表取締役社長に就任
VISAと提携。エポスカードの発行を開始
ハウスカードのLTV問題
1960年代のクレジットカードの発行以来、丸井は来店者に対して赤いカードをハウスカードとして発行していた。店舗における即時発行が可能な一方で、利用先は丸井店舗に限られてしまうという制約があり、顧客が丸井で買い物をしなくなると会員離脱が発生する問題が生じていた。
特に、丸井の商品は20代の若い層がターゲットとなっており、平均的に30歳以上になるとカードが使われなくなる問題があった。そこで、丸井はクレジットカードを外部店舗でも利用できる汎用的なカードとして提供することを計画した。
VISA提携カード「エポスカード」の発行
2006年4月に丸井は「エポスカード」の発行を開始。VISA提携カードとして他の加盟店で利用可能なクレジットカードであり、丸井店舗からの卒業後も、クレジットカードの外部店舗での利用による会員維持を目論んだ。また、従来の丸井のハウスカードの強みであった店舗での即時発行を可能にするために、2005年にVISAからスペシャルライセンシーを取得し、カード発行の独自システム構築を実施した。
丸井としてはエポスカードの発行によって、外部加盟店からの手数料収入、ショッピングリボ払いによる顧客からの手数料収入の増大を合わせて目論んだ。
エポスカードへの会員転換が進捗
2006年のエポスカードの発行と同時に、ハウスカードからの会員転換を実施。5年が経過した2011年度には旧カードの比率が10%未満となり、エポスカードへの転換をほぼ完了した。
カード取扱高の面では、丸井店舗における取扱高は1200億円前後で低迷した一方、外部加盟店での利用が拡大。エポスカードによって、丸井店舗における業績低迷をカバーする形となった。加えて、収益性が高いリボ払いによる手数料収入も増大させた。
エポスカードの取扱高が増加したことにより、丸井が保有する債権「割賦売掛金」が増加。FY2016における割賦売掛金の期末残高は3491億円であり、営業キャッシュフローにおける「割賦売掛金の増減額」は684億円の増加となり、営業CFは▲459億円となった。
キャッシングから手数料ビジネスに転換
2006年までの丸井はキャッシングによる消費者ローンが収益を支えていたが、エポスカードの発行を通じて「割賦手数料(=分割)」と「加盟店手数料」の2つが収益源に成長。2006年以降、改正貸金業法による利息返還問題(グレーゾーン金利問題)に直面したが、エポスカードによる手数料収入の確保により、業態転換で収益確保に成功した。
エポスカードはVISAから直接ライセンスを取得して、丸井以外でも世界中どこでも使えるカードで、ちょうど貸金業法改正とほぼ同時にスタートしました。そこから、キャッシングの利益がガーッと減っていく一方で、カードビジネスの加盟店手数料や分割手数料がグーッと上がってきて、7年後に元の水準ぐらいまで稼げる状態になり、8年目から増益に転じることができたんです。
改正貸金業法により財務体質が悪化
違法徴収分の利息分の返還開始
2006年12月に改正貸金業法が施行され、利息がグレーゾーン金利から17%へと引き下げられた。この結果、丸井はキャッシング事業において莫大な利息返還に応じる必要が生じ、引当金の状況によっては財務危機に陥る可能性もあった。改正貸金業法の施行を受けて、丸井はキャッシング事業(営業貸付金)を縮小する道を選択した。
2007年時点で丸井はキャッシング残高2500億円であり、貸出金利が1%低下するだけで年間利益が25億円失われることが想定され、キャッシングを収益源とした丸井にとって打撃となった。
利息返還により15か年で累計1247億円の損失
2006年3月期から丸井は「利息返還請求」に備えた引当金として「利息返還引当金繰入額」の損失計上を開始した。2021年3月期までの15年にわたって、累計1247億円の「利息返還引当金繰入額」を損失計上した。
制度がコロコロ変わるため、会社と社員の信頼関係はほぼなかったと思います。そこに06年の貸金業法改正という想定の3倍以上のマグニチュードの激震が襲ってきた。上限金利の引き下げなどで金融・カード事業が大打撃を受け、絶体絶命。いつつぶれてもおかしくない、いつ競合から買収されてもおかしくない状態でした
ところが社内の雰囲気は『ヤング・ファッション・赤いカード』という1980年代の成功体験が忘れられず、これを変えたら丸井じゃなくなる、と変化に対する抵抗がすごく強かった。過去の成功が会社のアイデンティティーになってしまっていたんです
不採算店舗の整理・最終赤字に転落
2011年3月期に丸井は最終赤字に転落。小売においては不採算店舗の閉鎖による減損計上に加え、2005年度以降の利息返還訴訟に対応するための引当金計上によりPLが悪化した。
大規模異動を実施・カード事業を強化
縮小する小売事業の効率向上のため、人員を「小売事業」から「カード事業・他」に移動
ベンチャー企業への出資・協業を本格化
11年連続増益を達成
2010年代を通じて丸井は青井浩社長のトップダウンによって経営再建に着手。小売業では仕入れ販売から賃貸型への転換、金融業では家賃保証などの手広いサービスを展開することによって収益を確保