| 期 | 区分 | 売上高 | 利益※ | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1961/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | 0億円 | - | - |
| 1962/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1963/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1964/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1965/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1966/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1967/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | 2億円 | 0億円 | 4.9% |
| 1968/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | 5億円 | 0億円 | 3.3% |
| 1969/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | 11億円 | 0億円 | 4.1% |
| 1970/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | 23億円 | - | - |
| 1971/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | 34億円 | - | - |
| 1972/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | 36億円 | - | - |
| 1973/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1974/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1975/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1976/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1977/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1978/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1979/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1980/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | 502億円 | - | - |
| 1981/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | 642億円 | - | - |
| 1982/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1983/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1984/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1985/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1986/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | 1,383億円 | - | - |
| 1987/12 | 単体 売上高 / 経常利益 | - | - | - |
| 1988/12 | 単体 売上高 / 当期利益 | 2,692億円 | 160億円 | 5.9% |
| 1989/12 | 単体 推定売上高 / 経常利益 | 2,900億円 | - | - |
| 1990/12 | 単体 推定売上高 / 経常利益 | 3,700億円 | - | - |
| 1991/12 | 単体 推定売上高 / 経常利益 | 3,600億円 | - | - |
| 1992/3 | 単体 推定売上高 / 経常利益 | 3,100億円 | - | - |
| 1993/3 | 単体 売上高 / 当期利益 | 3,039億円 | 31億円 | 1.0% |
| 1994/3 | 単体 売上高 / 当期利益 | 2,648億円 | 20億円 | 0.7% |
| 1995/3 | 単体 推定売上高 / 経常利益 | 2,700億円 | - | - |
| 1996/3 | 単体 推定売上高 / 経常利益 | 3,000億円 | - | - |
| 1997/3 | 単体 推定売上高 / 経常利益 | 3,300億円 | - | - |
| 1998/3 | 単体 推定売上高 / 経常利益 | 3,400億円 | - | - |
| 1999/3 | 単体 営業収益 / 経常利益 | 2,889億円 | 718億円 | 24.8% |
| 2000/3 | 単体 営業収益 / 経常利益 | 2,808億円 | 845億円 | 30.0% |
| 2001/3 | 単体 営業収益 / 経常利益 | 3,265億円 | 1,012億円 | 30.9% |
| 2002/3 | 単体 営業収益 / 経常利益 | 3,221億円 | 976億円 | 30.3% |
| 2003/3 | 単体 営業収益 / 経常利益 | 3,081億円 | 955億円 | 30.9% |
| 2004/3 | 単体 営業収益 / 経常利益 | 3,622億円 | 1,114億円 | 30.7% |
| 2005/3 | 単体 売上高 / 経常利益 | 4,078億円 | 1,223億円 | 29.9% |
| 2006/3 | 単体 売上高 / 経常利益 | 4,436億円 | 1,302億円 | 29.3% |
| 2007/3 | 連結 売上高 / 経常利益 | 7,569億円 | 1,614億円 | 21.3% |
| 2008/3 | 連結 売上高 / 経常利益 | 10,066億円 | 1,629億円 | 16.1% |
| 2009/3 | 連結 売上高 / 経常利益 | 10,839億円 | 1,124億円 | 10.3% |
| 2010/3 | 連結 売上高 / 経常利益 | 7,933億円 | 710億円 | 8.9% |
| 2011/3 | 連結 売上高 / 経常利益 | 7,526億円 | 902億円 | 11.9% |
| 2012/3 | 連結 売上高 / 経常利益 | 8,066億円 | 1,176億円 | 14.5% |
| 2013/3 | 連結 売上高 / 経常利益 | 10,492億円 | 1,281億円 | 12.2% |
| 2014/3 | 連結 売上高 / 経常利益 | 11,915億円 | 1,220億円 | 10.2% |
| 2015/3 | 連結 売上高 / 経常利益 | 12,999億円 | 1,256億円 | 9.6% |
| 2016/3 | 連結 売上高 / 経常利益 | 15,886億円 | 1,193億円 | 7.5% |
| 2017/3 | 連結 売上高 / 経常利益 | 18,399億円 | 1,317億円 | 7.1% |
| 2018/3 | 連結 売上収益 / 税引前利益 | 21,733億円 | 1,992億円 | 9.1% |
| 2019/3 | 連結 売上収益 / 税引前利益 | 23,107億円 | 2,398億円 | 10.3% |
| 2020/3 | 連結 売上収益 / 税引前利益 | 23,994億円 | 2,261億円 | 9.4% |
| 2021/3 | 連結 売上収益 / 税引前利益 | 22,693億円 | 1,685億円 | 7.4% |
| 2022/3 | 連結 売上収益 / 税引前利益 | 28,717億円 | 3,827億円 | 13.3% |
| 2023/3 | 連結 売上収益 / 税引前利益 | 34,295億円 | 3,677億円 | 10.7% |
Author's Insights
リクルートは「人材輩出企業」「起業家精神」といった華やかなイメージで語られることが多い。しかし1990年代から2000年代にかけて、経営の実態は極めてシビアな財務再建の渦中にあった。バブル崩壊後、子会社リクルートコスモスの不動産含み損を本体で引き受け、有利子負債は1995年に1.4兆円に達した。非上場企業であったため株式市場からの資金調達という選択肢はなく、返済原資は本業の営業利益と銀行借入の借り換えに限られた。当時の営業利益は約600億円規模であり、単純計算では完済に20年以上を要する水準だった。現場の社員が活気ある営業文化の中で働く一方、CFOやCEOが見ていた景色は「毎年の利益をどう返済に回すか」という資金繰りの世界だった。
再建を可能にしたのは、本業の収益構造そのものである。就職情報誌・住宅情報・じゃらん・ゼクシィといった媒体群は、掲載料を広告主から受け取るモデルであり、在庫リスクや大規模設備投資を必要としない。売上に対する限界利益率が高く、営業人員の増減で収益を調整しやすい構造を持っていた。さらに1997年に導入されたOPT制度(30歳以上の退職者に1000万円加算)も、社員には「独立支援」として受け止められたが、経営側から見れば1.4兆円の債務返済のために固定費を圧縮する財務施策であった。現場が感じる企業文化と、経営陣が直面する財務現実の間には、大きな温度差が存在していた。
加えて、返済期間中も事業投資を完全に止めたわけではない点が重要である。2001年にはホットペッパーを創刊して狭域ビジネスに参入し、人材派遣のリクルートスタッフィングを拡大し、2007年にはスタッフサービスHDを買収している。債務圧縮と事業拡張を同時に進行させたのは、本業のキャッシュ創出力に余裕があったからこそ可能だった。返済のために縮小均衡に陥るのではなく、返済しながら次の収益源を仕込む。この二正面作戦を成立させた背景には、投下資本の小さい情報サービスという事業モデルの特性がある。外から見れば攻めの経営に映る事業拡大も、内側から見れば返済原資を増やすためのキャッシュ創出力の強化だった。
リクルートの財務再建が示しているのは、致命的な負債を抱えても本業が十分に強ければ企業は生き残れるという原則である。同じ負債を製造業や小売業が抱えていれば、再建は困難だったと考えられる。リクルートの再建は「意志の力」ではなく「収益構造の力」で実現されたものであり、事業モデルの選択が企業の生存力を規定するという構造的な教訓を示唆している。そして、社員が見る「自由闊達な企業文化」と、経営陣が見る「1.4兆円の返済計画」がまったく異なる風景として同時に存在していたこと自体が、この企業の特異さを物語っている。
2012年のIndeed買収は、リクルートを国内情報誌企業からグローバルHRテクノロジー企業へと転換させた決定的な意思決定だった。しかしこの案件は、トップダウンの戦略策定から生まれたものではない。買収候補にIndeedを挙げたのは、当時36歳で新規事業を担当していた出木場久征氏であった。米国発の求人検索エンジンは日本ではほぼ無名だったが、出木場氏は創業者と事業モデルに将来性を見出し、社内で強く買収を推した。1000億円超の巨額案件の起点が、個人の熱量と目利きにあったという事実は注目に値する。
社内では議論が分かれた。安定収益を持つ派遣会社の買収案と比較され、赤字のテクノロジー企業に1000億円を投じることへの慎重論は当然あった。Indeedは従業員約550名、売上は100〜200億円規模と推定される一方で、広告投資と開発費で赤字を計上していた。DDも数週間から1か月という短期間で行われており、通常の大型M&Aのプロセスとは異なるスピード感だった。峰岸真澄CEOは、テクノロジーがHRの構造を変えるという前提に賭けて買収を決断した。提案者の熱量を、経営トップが受け止めて最終判断に変換する。この二段構えの意思決定プロセスが機能した。
買収後のPMIにおいて決定的だったのは、提案者である出木場氏自身がIndeedのCEOに就任し、現地に常駐して事業を率いた点である。M&Aの世界では、買収案件を発掘・提案した担当者がクロージング後に別の案件探索へ移ったり、退職したりするケースは珍しくない。「見つける人」と「育てる人」が分離する構造では、買収時の事業理解や関係性が引き継がれず、PMIが形骸化する原因となりがちである。リクルートの場合、提案した本人が責任を持って買収先に入り込み、Indeedの経営陣とエンジニア組織に大幅な裁量を委ねながら成長を牽引した。「言い出した者がやる」という組織文化が、巨額M&Aの成否を分けた。
Indeedの事例が浮かび上がらせるのは、巨額M&Aの成否を分けるのは財務分析の精度だけではなく、「誰が提案し、誰が実行し、誰が最後まで責任を持つか」という人の要素だという点である。戦略コンサルが描いたロードマップでもなく、投資銀行が持ち込んだディールでもなく、現場に近い人間が肌感覚で見出した機会を経営トップが信じて賭けた。そして提案者自身が買収先の経営を完遂した。この一連の流れは、組織として再現可能な仕組みというよりも、提案者の熱量と経営者の胆力が噛み合った結果かもしれない。ただし、そうした個人の動きを許容し、巨額の意思決定につなげ、提案者に最後まで任せきる組織構造を持っていたこと自体が、リクルートの競争力の一端を示している。
大学新聞広告社を個人創業
23歳の江副浩正が大手銀行に門前払いされた後、芝信用金庫から引き出した300万円の融資が事業の出発点となった。担保は父の土地と家屋であり、自己資金ではなく他人資本で起業する構造は創業時から組み込まれていた。資本金60万円・初年度売上450万円という規模感は、後年の1.4兆円の有利子負債と対照的だが、借入で事業を回すという行動様式の起点はここにある。
背景:高度成長前夜の就職情報空白
1960年前後の日本は高度経済成長の入り口にあり、大学進学者数も増加していた。しかし企業と学生を結ぶ就職情報の流通経路は未整備で、採用活動は教授推薦や縁故に依存する側面が強かった。企業側も学生へ直接情報を届ける手段を十分に持たず、採用市場には構造的な情報の非対称性が存在していた。
特に中堅・中小企業は自社の求人情報を学生へ届ける手段に乏しく、大学単位での体系的な情報媒体は存在していなかった。新聞広告は一般向けであり、学生市場に特化した広告媒体は未開拓領域であった。この隙間が事業機会となった。
決断:信用なき創業と資金調達
1960年、江副浩正は大学新聞広告社を個人創業した。しかし創業当初は実績も信用もなく、大手銀行からは相手にされなかった。事業資金を確保するため、芝信用金庫田村町支店へ直接足を運び、事業の必要性を繰り返し説明した。
父が所有していた土地と家屋を担保に差し入れ、二度目の交渉で300万円の融資を取り付けた。窓口担当者は「あなたのやろうとしている仕事は間違いない」と背中を押したという。この融資をもとに事業運転資金を確保し、営業活動を開始した。
結果:資金確保による事業継続
300万円の融資は、創業期の運転資金として活用された。大学新聞への広告掲載を進める営業活動が本格化し、企業からの広告受注が徐々に増加した。資金確保により、継続的な営業活動が可能となった。
広告取扱件数は拡大し、複数大学との取引が進展した。事業は個人事業として継続され、その後法人化へと移行した。このため、リクルートは資金難からの創業を金融機関からの借入によって乗り越えたことから、後年バブル期の借金体質構造(借入による土地取得)の原点にもなった。
23歳の江副浩正が大手銀行に門前払いされた後、芝信用金庫から引き出した300万円の融資が事業の出発点となった。担保は父の土地と家屋であり、自己資金ではなく他人資本で起業する構造は創業時から組み込まれていた。資本金60万円・初年度売上450万円という規模感は、後年の1.4兆円の有利子負債と対照的だが、借入で事業を回すという行動様式の起点はここにある。
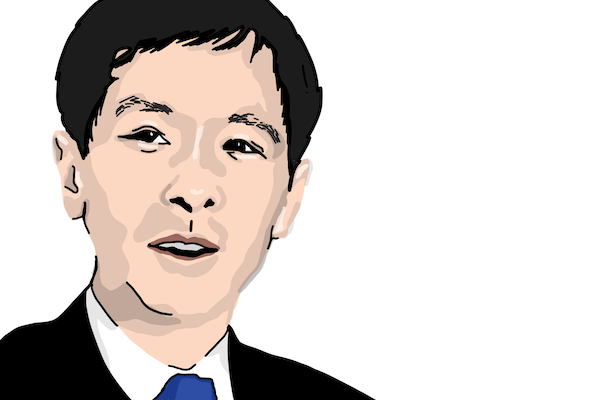
創業当初で信用力はないし、大手の銀行は相手にしてくれない。ということで、芝信用金庫の田村町支店にお願いに行きまして、「これだけの一流企業がこの仕事の必要性を認めているんです。ぜひ面倒を見てください」と頼み込みましてね。もちろん、父が人に貸していた土地、家屋を担保にしての借入だったが、窓口の人の理解がありまして「担保能力はないし、支店長は心配していたけど、私は、あなたのやろうとしている仕事は絶対に間違いない。あなたなら間違いない、と確信して頑張ったんですよ」と、2回目のお願いで300万円の融資を了承してもらった。あの時の言葉は一生、耳にこびりついて離れないでしょうね。
就職情報誌「企業への招待」を創刊
創刊号66社の掲載は、1日12〜13社を訪問し成約率10%という泥臭い営業の積み重ねで実現された。広告代理と媒体発行を自社で兼ねる構造は、他社の代理店経由モデルとは異なり、営業と編集の距離が近い。1966年にダイヤモンド社が売上規模で上回る競合として参入した後も、訪問件数で勝負する体質が定着した。この営業主導の組織文化は、後年のホットペッパーやリクナビにも引き継がれている。
背景:冊子媒体化と競争環境
1962年に就職情報誌「企業への招待」を創刊し、大学新聞広告から冊子媒体へと発展させた。学生に対してはダイレクトメールで希望者を募り、当初から1000名以上へ配布する体制を整えた。掲載企業からの広告料を収益源とするモデルが確立され、冊子単位での販売が始まった。
同誌は媒体を自社で制作しながら、広告主も自ら開拓する体制を採用した。広告代理と媒体発行を分業しない構造であった。その後、1966年にはダイヤモンド社が「就職ガイド」で参入し、売上規模で大きく上回る競合との競争環境に入った。
決断:広告主開拓の徹底強化
創刊号では66社の掲載を実現したが、営業活動は高い成約率ではなかった。都内で1日12〜13社を訪問し、商談に進むのは6〜7社のうち1社、最終的な成約は10社に1社という打率であった。訪問件数を増やすことが前提となった。
見込み顧客である大企業を中心に足で稼ぐ営業を徹底し、企業約200社を訪問して誌面構成や掲載量について意見を聞きながら改良を重ねた。営業活動と媒体改善を同時に進める体制が構築された。
結果:新市場開拓と営業体質の定着
冊子は発行部数を拡大し、1960年代後半には年間17万部規模へ到達した。学生向け就職情報誌という新たな市場が形成され、企業広告を集約する媒体として定着した。ただし競争環境は継続し、市場を独占する状況には至らなかった。
ダイヤモンド社との競争下で、営業力を軸に受注を積み上げる体質が組織に根付いた。訪問件数を増やし、足で開拓する営業スタイルが標準化され、以後の事業展開においても営業主導の組織文化が継続した。
創刊号66社の掲載は、1日12〜13社を訪問し成約率10%という泥臭い営業の積み重ねで実現された。広告代理と媒体発行を自社で兼ねる構造は、他社の代理店経由モデルとは異なり、営業と編集の距離が近い。1966年にダイヤモンド社が売上規模で上回る競合として参入した後も、訪問件数で勝負する体質が定着した。この営業主導の組織文化は、後年のホットペッパーやリクナビにも引き継がれている。
我々がこの仕事を始めた時、持っていたものといえば、わずかな広告営業の経験と印刷知識だけで、ゼロからのスタートに等しかった。(略)「リクルートブック」を創刊するときにも、どうすれば良いか何もわからなかったので、当然のことながら、「わからないことはお客様に聞く」という方法をとった。大学新聞で取引のあった会社を中心に、200社ばかりの企業を訪ね、採用担当者に直接、意見を聞いて回った。「配本の対象大学はどこに」「事務系と技術系は分けた方がいいか」あるいは「掲載量はいくらぐらいなら参画してもらえるか」と言ったことである。ツカ見本を作って、紙質の良否まで、見込み客に聞いて回った。
当初予想していたよりも企業側の見込み客は総じて好意的で、積極的に意見を提供していただいた方も少なくなかった。
分譲マンション販売を開始
1974年に長谷川工務店からの持ち込みで始まった分譲マンション事業は、1987年に売上高1757億円・販売戸数4333戸(国内2位)に達し、情報誌を主力とする親会社を上回る規模に膨張した。情報を扱う企業が有形資産の保有に傾斜した結果、リクルートコスモスの株式公開問題がリクルート事件に発展し、バブル崩壊後は約3500億円の不動産を本体が引き取る事態に至った。1.4兆円の有利子負債の直接的な発生源である。
背景:情報企業から資産保有へ
1971年、リクルートは西新橋に本社ビルを竣工し、土地を取得した。投資額は約11億円。当時の主力は就職情報誌であり、同社は無形の情報を扱う企業だったが、土地という有形資産を自社で保有する判断は、信用力の補完と財務基盤の強化を同時に狙ったものであった。高度成長期の地価上昇を背景に、不動産は単なるオフィス確保ではなく、資産形成と事業機会の両面を持つ対象として認識された。
情報誌事業で蓄積した営業力と顧客接点を活かせば、若い産業であったマンション市場にも参入可能と判断された。1960年代後半から都市部で分譲住宅需要が拡大する中、不動産は情報に次ぐ第二の柱になり得るとの見立てが形成された。
決断:リクルートコスモスで本格展開
1974年、長谷川工務店から「ネオコーポ行徳」の販売を持ちかけられたことを契機に、分譲マンション事業へ本格参入した。江副浩正と同社副社長の旧知の縁が入口であったが、事業化の決断は市場規模と成長余地を踏まえたものであった。
事業は本体から切り離し、リクルートコスモスを通じて展開された。1970年代後半から1980年代にかけて用地取得を加速し、販売戸数を拡大。1986年には販売戸数4333戸で国内2位に到達し、1987年には売上高1757億円を記録し親会社を上回った。不動産は情報誌と並ぶ主力事業へ成長した。
結果:拡大の代償と売却
急拡大の過程で、リクルートコスモスの株式公開を巡る問題が発覚し、いわゆるリクルート事件へ発展した。社会的信用の毀損はグループ全体に波及し、経営体制の見直しを迫られた。
さらにバブル崩壊による地価下落で巨額損失を計上し、1990年代を通じてリクルートは不動産事業の失敗により、積極投資を封じられる苦境に陥った。不動産事業は財務リスクの根本原因となり、2000年代のグループの再建過程でリクルートコスモスは切り離され、最終的に株式売却へと至った。不動産事業は縮小され、リクルートは再び情報・人材領域を中核とする体制へ回帰することになった。
1974年に長谷川工務店からの持ち込みで始まった分譲マンション事業は、1987年に売上高1757億円・販売戸数4333戸(国内2位)に達し、情報誌を主力とする親会社を上回る規模に膨張した。情報を扱う企業が有形資産の保有に傾斜した結果、リクルートコスモスの株式公開問題がリクルート事件に発展し、バブル崩壊後は約3500億円の不動産を本体が引き取る事態に至った。1.4兆円の有利子負債の直接的な発生源である。
たまたま昭和49年に、長谷川工務店が建てたネオコーポ行徳の販売を引き受けたのが事業のこう矢である。リクルート・グループの創始者で当社の現会長の江副浩正が、中学以来の親友である長谷川工務店の合田副社長から、「ネオコーポ行徳をリクルートで売ってみないか」と言われ、もし売れ残ったら当社の社宅にして良い、ぐらいの気持ちでスタートした事業である。だが、事業を進めるにつれ、マーケット・チャンスの大きさを確信してきた。マンション事業は昭和40年代に始まった若い産業なので、当社のような後発組でも、研究と工夫を重ねれば、業界のトップまで行けるのではないかと、産業の若さに着目したのである。
住宅情報を創刊(現SUUMO)
1ページ104万円の掲載料と200円の雑誌売価で構成された収益モデルは、就職情報誌と同一の構造である。創刊から11号まで赤字が続いたが、12号で黒字化し、1982年には週刊化・22万部・売上150億円に到達した。おとり物件排除のための情報審査部を設置し、媒体の信頼性を広告単価の根拠としている。住宅情報が祖業の271億円に迫る154億円規模に成長したことで、リクルートは就職情報専業から「ライフイベント情報企業」へ転換する足がかりを得た。
背景:不動産広告の拡大に着目
1970年代、分譲マンションや郊外戸建ての需要が拡大し、新聞やテレビにおける不動産広告の比率が上昇していた。江副浩正はこの変化に着目し、広告が氾濫する一方で、供給者と需要者を体系的に結びつける媒体が存在しない点を機会と捉えた。
就職情報で確立した「媒体を自社で持ち、広告主を自ら開拓する」モデルを不動産領域へ転用すれば、新たな市場を創出できると判断。1976年1月、首都圏向け月刊誌「住宅情報」を創刊し、就職情報からの多角化に踏み出した。
決断:広告モデルと品質管理の構築
住宅情報の収益源は、掲載広告(1ページ104万円)と雑誌売価200円で構成された。1冊あたり売上は1363円となり、広告主からの掲載料を軸とするビジネスモデルを採用した。創刊から11カ月は赤字が続いたが、12号発刊時に認知度が高まり黒字化を達成した。
物件掲載が増えるほど読者が増え、読者が増えるほど広告主が増える循環を形成するため、「情報審査部」を設置し、おとり物件を排除する体制を整備。媒体価値を守ることで、広告単価の維持と掲載件数拡大を同時に実現した。
結果:祖業に匹敵する柱へ成長
1982年頃には首都圏版を週刊化し、発行部数は22万部に拡大。同年12月期の売上高は150億円に到達し、前年の約2倍の成長を記録した。住宅情報事業は短期間で急拡大し、情報誌事業の中核へと浮上した。
1981年時点で住宅情報は154億円規模となり、祖業である広告事業271億円に迫る存在となった。これにより、リクルートは就職情報専業から脱却し、「生活情報を扱う企業」へと事業構成を転換する契機を得た。
1ページ104万円の掲載料と200円の雑誌売価で構成された収益モデルは、就職情報誌と同一の構造である。創刊から11号まで赤字が続いたが、12号で黒字化し、1982年には週刊化・22万部・売上150億円に到達した。おとり物件排除のための情報審査部を設置し、媒体の信頼性を広告単価の根拠としている。住宅情報が祖業の271億円に迫る154億円規模に成長したことで、リクルートは就職情報専業から「ライフイベント情報企業」へ転換する足がかりを得た。
新聞、テレビであれだけ氾濫している住宅広告・CMだ。うちの「住宅情報」はツーウェイ・コミュニケーション。供給者と需要者を結びつける理想的な形のはず。必ず世に受け入れられる。
銀座本社ビルを取得
1984年12月期の資産合計2756億円に対し有利子負債1998億円、負債比率72.4%。情報誌事業で年間経常利益150億円を稼ぎながら、その数倍の借入金で銀座周辺の不動産を取得した。当時の常務が「自己資本比率のビジョンはない」と公言する財務姿勢が象徴的である。含み益が担保として機能する地価上昇局面だからこそ成立した構造であり、この借入拡大型の資産膨張が後年の1.4兆円有利子負債の直接の布石となった。
背景:土地取得による信用力の強化
1980年代に入り、リクルートは情報誌事業の拡大と並行して、都心部における土地取得を積極化した。とりわけ銀座周辺は企業イメージを高める象徴的な立地であり、本社機能を自社保有ビルに集約することで、企業としての信用力と社会的存在感を高める狙いがあった。
1980年頃には日本軽金属から銀座のビルを約200億円で取得し、本社ビル「G8」として活用を開始。以後も銀座・新橋エリアでの用地取得を進め、情報誌企業から総合不動産保有企業へと資産構成を拡張していった。
決断:借入によるレバレッジ拡大
数百億円規模の資金需要に対し、リクルートは自己資金ではなく銀行借入による調達を選択した。1983年度から1984年度にかけて約1000億円を借り入れ、不動産取得を加速。積極的なレバレッジ戦略をとることで、短期間で資産規模を拡大した。
1984年12月期時点で、単体資産合計2756億円に対し、有利子負債は1998億円に達し、負債比率は72.4%に上昇。自己資本比率よりも資産拡大を優先する財務運営へと舵を切った。
結果:含み益前提の財務構造へ
銀行が大規模融資に応じた背景には、情報誌事業で年間経常利益150億円規模を確保していた収益力と、当時の地価上昇局面があった。不動産価格の上昇が継続する前提のもと、土地の含み益が実質的な担保として機能していた。
その結果、リクルートは高収益の情報誌事業を基盤にしつつ、土地資産と負債を同時に膨張させる構造へ移行。資産拡大型の財務体質は、その後の経営リスクの増幅要因にもつながる布石となった。
1984年12月期の資産合計2756億円に対し有利子負債1998億円、負債比率72.4%。情報誌事業で年間経常利益150億円を稼ぎながら、その数倍の借入金で銀座周辺の不動産を取得した。当時の常務が「自己資本比率のビジョンはない」と公言する財務姿勢が象徴的である。含み益が担保として機能する地価上昇局面だからこそ成立した構造であり、この借入拡大型の資産膨張が後年の1.4兆円有利子負債の直接の布石となった。
自己資本比率を何%に持って行こうなどという財務バランスについてもビジョンは当社にはありません。必要な資金は可能な限り都合をつけます。
リクルート事件が発覚
リクルートコスモスの未公開株譲渡が政財界を巻き込むスキャンダルに発展し、江副浩正は1988年に社長辞任、1989年に逮捕、2003年に有罪確定に至った。経営上の最大の影響は、事件処理に追われた結果、不動産事業からの撤退判断が遅れたことにある。バブル崩壊前に不動産を圧縮していれば負債規模は大幅に縮小できた可能性があるが、創業者退任直後の混乱期にそうした決断は困難だった。
背景:未公開株取引と拡大路線
1980年代後半、リクルートは情報誌事業と不動産事業の両輪で急成長を遂げていた。子会社リクルートコスモスは店頭公開を果たし、未公開株の価値が急騰する局面にあった。株式公開前の段階で有力政治家や官僚に株式を譲渡していた事実が後に問題視されることになる。
当時は未公開株の割当自体が直ちに違法とされる明確な規制が整っていなかったが、政財界との密接な関係の中で行われた取引は社会的な疑念を招いた。バブル景気の高揚感の中で拡大を続けていた経営体制は、統治の透明性という観点で脆弱性を抱えていた。
決断:創業者退任と体制刷新
1988年、リクルートコスモスの未公開株譲渡問題が発覚し、日本の政財界を巻き込む大規模なスキャンダルへ発展した。社会的批判が高まる中、創業者である江副浩正は責任を取る形で社長を辞任し、経営の第一線から退く決断を迫られた。
1989年には江副氏が収賄容疑で逮捕され、企業イメージは大きく毀損した。後任社長には位田氏が就任し、本業である情報誌事業への回帰と企業理念の再整備を掲げ、信用回復を最優先課題とする経営方針へと転換した。
結果:信用失墜と財務負担の顕在化
事件によりリクルートの社会的信頼は大きく失われ、取引先や金融機関との関係にも影響が及んだ。さらに、不動産事業からの撤退を即断できなかったことが、後のバブル崩壊局面で深刻な財務負担として顕在化することとなる。
1990年代初頭の地価下落によりリクルートコスモスの含み益は消滅し、巨額の有利子負債が残存した。本社がグループを支える構図となり、長期にわたる財務再建局面へ移行した。2003年に江副氏の有罪判決が確定し、2013年に76歳で逝去した。
リクルートコスモスの未公開株譲渡が政財界を巻き込むスキャンダルに発展し、江副浩正は1988年に社長辞任、1989年に逮捕、2003年に有罪確定に至った。経営上の最大の影響は、事件処理に追われた結果、不動産事業からの撤退判断が遅れたことにある。バブル崩壊前に不動産を圧縮していれば負債規模は大幅に縮小できた可能性があるが、創業者退任直後の混乱期にそうした決断は困難だった。
ダイエーがリクルートの株式を取得
江副氏が保有株35.2%をダイエーに455億円で売却し、リクルートはダイエーの関係会社となった。非上場企業における大口株式の移動であり、経営陣との合意なく進められたため社内対立を招いた。2000年前後にダイエーが経営危機に陥ると、リクルートは25.2%を約1000億円で買い戻し、残り10%も2006年までに処理した。売却額455億円に対し買戻し総額は約1550億円となり、独立回帰に要したコストの大きさが際立つ。
背景:創業者株式処理の難題
1988年のリクルート事件後、創業者である江副浩正は経営の第一線を退いたが、依然として大量の株式を保有していた。リクルートは非上場企業であり、株式の流動性が乏しかったため、創業者が持分を処分する場合、その引受先の選定は会社の支配構造に直結する重大な問題となった。
さらに、不動産事業の負債問題や社会的信用の毀損が残る中で、資本の安定化は急務であった。銀行管理下に置かれる可能性も議論される状況下で、創業者の持株処理は単なる個人の資産売却ではなく、リクルートの将来の独立性を左右する資本政策上の課題であった。
決断:ダイエーへ三五%売却
1992年、江副氏は自ら保有していたリクルート株式35.2%を大手小売業ダイエーへ売却した。売却額は約455億円とされ、この結果リクルートはダイエーの関係会社となった。非上場企業における大口株式の移動は、経営権の帰趨に影響を及ぼす重大な転換であった。
しかし、この売却は現経営陣との十分な合意形成を経ずに進められたため、後任社長の位田氏との間で深刻な対立が生じた。独立路線を志向する経営陣と、ダイエーとの連携を容認する創業者の立場は交わらず、資本構造を巡る緊張関係が社内外に広がった。
結果:買戻しで独立回帰へ
ダイエーの資本参加は一時的に安定株主を得た形となったが、両社の経営方針は必ずしも一致しなかった。その後、2000年前後にダイエーが経営危機に陥ると、リクルートは資本関係の整理に着手し、約1000億円で25.2%を買い戻した。
残る約10%の株式も2006年までに金融機関などへ売却され、ダイエーとの資本関係は解消された。こうしてリクルートは再び独立経営に回帰し、資本構造の整理を経て、のちの株式上場へと向かう基盤を整えることになった。
江副氏が保有株35.2%をダイエーに455億円で売却し、リクルートはダイエーの関係会社となった。非上場企業における大口株式の移動であり、経営陣との合意なく進められたため社内対立を招いた。2000年前後にダイエーが経営危機に陥ると、リクルートは25.2%を約1000億円で買い戻し、残り10%も2006年までに処理した。売却額455億円に対し買戻し総額は約1550億円となり、独立回帰に要したコストの大きさが際立つ。
ダイエーへの株式売却は・・
江副氏:リクルートが銀行管理下に置かれるよりも、ダイエーグループ入りした方が従業員にとって幸せと考えた。
位田氏:銀行管理下に置かれる状況に至っていない。リクルートグループは自主再建できる。株式売却は株主の一人がダイエーに代わっただけのことに過ぎない。
グループ再建について
江副氏:リクルート、リクルートファイナンスは兄弟関係にあるのだから、仲良く協力して再建に取り組んでほしい
位田氏:債務保証はしていないし、法的に面倒を見なければいけないという義務はない。役員会の了承を得て、リクルートにとってマイナスにならない範囲で支援する。
ダイエーとの人材交流について
江副氏:親戚となった以上は、例えばリクルートコスモスの社員が出向しても良いと思う
位田氏:こちらから人を出す気はないし、ダイエーからも役員以外の派遣もあり得ない
有利子負債1.4兆円
1995年3月期末の有利子負債1.4兆円に対し、当時の営業利益は約600億円。単純計算で完済に20年以上を要する水準だった。非上場のため株式市場からの調達手段はなく、返済原資は本業の営業利益と借換に限られた。実際には情報誌・人材派遣の収益力強化で2000年代半ばに営業利益1000億円規模に到達し、2007年3月期末には有利子負債375億円まで圧縮した。12年間で約1兆3600億円を返済した計算になる。
背景:不動産救済で債務膨張
バブル崩壊により、グループ会社リクルートコスモスの不動産含み益は消滅し、巨額の有利子負債が表面化した。倒産を回避するため、リクルート本社は債務を実質的に肩代わりする道を選択し、財務負担を自社に集中させた。結果として、グループ再建は本社の信用力と収益力に依存する構図となった。
非上場企業であったリクルートは、株式市場からの資金調達という選択肢を持たず、本業収益と金融機関借入に依存する体制であった。地価下落が続く中で資産価値は毀損し、負債は膨張する。1995年3月期末、有利子負債は1.4兆円に達し、資産に対する負債比率も極めて高い水準に上昇した。
決断:返済優先の経営方針
1995年当時の営業利益は約600億円規模であり、単純計算では完済まで20年以上を要する水準であった。それでも経営陣は拡大よりも返済を優先する方針を明確にし、本業強化によるキャッシュ創出に経営資源を集中させた。再投資は最小限に抑え、財務の立て直しを最優先課題とした。
あわせて、不良資産の再評価を進めるため特別損失を段階的に計上し、バランスシートの圧縮を図った。一括処理では債務超過に陥る可能性があったため、時間をかけて資産を整理する方法を選択した。銀行団との協調の下、長期的な返済計画に基づく再建路線を採用した。
結果:長期再建と体質転換
1990年代から2000年代にかけて、本業で生まれた収益は継続的に返済へ充当された。投下資本の小さい情報サービスや人材派遣領域を強化し、キャッシュ創出力を高めることで、着実に負債を圧縮した。2000年代半ばには営業利益は1000億円規模へ拡大し、返済ペースは加速した。
その結果、2007年3月期末には有利子負債は375億円まで減少し、財務体質の健全化を実質的に完了した。ただし、その過程で大型買収や積極投資は制約され、成長戦略は抑制的であった。1.4兆円の債務は、企業の意思決定を長期にわたり規定する重荷となった。
1995年3月期末の有利子負債1.4兆円に対し、当時の営業利益は約600億円。単純計算で完済に20年以上を要する水準だった。非上場のため株式市場からの調達手段はなく、返済原資は本業の営業利益と借換に限られた。実際には情報誌・人材派遣の収益力強化で2000年代半ばに営業利益1000億円規模に到達し、2007年3月期末には有利子負債375億円まで圧縮した。12年間で約1兆3600億円を返済した計算になる。
OPT制度を導入
30歳以上の退職者に1000万円を加算するOPT制度は、社員には「独立支援」として受容されたが、経営側から見れば1.4兆円の債務返済のための固定費圧縮策である。5500人規模から約3000人に組織を再編し、離職率6〜8%で回すことで若手中心のピラミッド構造を維持した。河野社長自身が「優秀な人が流出しているのではないか」と懸念を表明しており、債務圧縮と人材流出のトレードオフを意識した上での判断だった。
背景:債務圧縮下の人件費構造
1990年代後半のリクルートは、1.4兆円に及ぶ有利子負債の圧縮を最優先課題としていた。財務再建を進める中で、固定費の抑制と高収益体質の維持が不可欠となり、とりわけ人件費構造の見直しが重要な経営テーマとなった。年功的に上昇する給与体系は、長期的にはコスト増要因となる構造を抱えていた。
同時に、情報サービス中心の事業は機動性と若手の活力を求める性質が強かった。組織をスリム化し、意思決定のスピードを維持することが競争力の源泉であると認識されていた。財務制約と事業特性の双方から、年齢構成と人員規模を戦略的に設計する必要が生じていた。
決断:OPT制度の導入
1997年、リクルートは30歳以上の社員が退職する際に退職金へ1000万円を加算するOPT制度を導入した。独立や転職を後押しする仕組みを整備することで、自然減による人員抑制と固定費の圧縮を同時に実現する狙いがあった。結果として組織は若手中心へと再構築されていった。
経営陣は優秀な人材流出への懸念を抱きながらも、財務再建との両立を優先した。離職率は6〜8%で推移し、過度な混乱は回避された。制度は「退職を促す仕組み」とも受け止められたが、巨額債務を抱える状況下では、高齢かつ高給層を抱え続ける選択は困難であった。
結果:人材輩出企業の形成
OPT制度により組織は約3000人規模へと再編され、機動性を維持した体制が確立された。若年層中心のピラミッド構造が形成され、成果主義と早期登用が進んだ。この人事設計は、事業拡大よりも収益性とキャッシュ創出力を重視する時代の要請に適応したものであった。
一方で、優秀人材が外部へ流出することも常態化し、リクルートは「人材輩出企業」として知られる存在となった。2010年代まで続いた制度は、2021年に廃止され方向転換が図られたが、1997年の決断は財務再建期における象徴的な組織戦略であった。
30歳以上の退職者に1000万円を加算するOPT制度は、社員には「独立支援」として受容されたが、経営側から見れば1.4兆円の債務返済のための固定費圧縮策である。5500人規模から約3000人に組織を再編し、離職率6〜8%で回すことで若手中心のピラミッド構造を維持した。河野社長自身が「優秀な人が流出しているのではないか」と懸念を表明しており、債務圧縮と人材流出のトレードオフを意識した上での判断だった。
ただ、昨今の私の心配は、離職率が6〜8%になりますと、やはり優秀な人が流出しているんじゃないかということです。実際、当社の決算を銀行の方に説明した時、「松永真里さんみたいな優秀な方も辞められたんですね」と、おたくは大丈夫ですかみたいなご質問をいただいたことがあります。社内にも(オプトとかフレックス選択定年は)やめてくれと言わんばかりの制度なので、もっと人を引き留めるグリップを強めようという意見があるんです。
もちろん、別の見方もあって、「ある時期に五千数百人もいたのが、今では3000人位で大変活性化している。非常に素晴らしい組織の再構築をされたんですね」なんて言われることもありますけれど。要するに2通りの見方があって難しいですね。
河野栄子氏が社長就任
1997年から2003年の河野体制は、営業利益率約30%を確保しつつ有利子負債を圧縮するという財務再建期の経営であった。テレアポから飛び込み営業へ転換し、提案型営業を定着させた営業改革の実績が就任の背景にある。在任中にネット関連の大型投資は限定的にとどまり、ECやIT領域で先行企業に差をつけられた面はあるが、1.4兆円の債務を抱えた状況下では新規投資に回す資金余力自体が乏しかった。
背景:財務再建下の経営継承
1990年代後半のリクルートは、1.4兆円規模の有利子負債を抱え、財務再建を最優先課題としていた。リクルート事件後の信頼回復と債務圧縮を同時に進める必要があり、経営には安定した本業収益の確保が求められていた。組織の求心力を保ちながら、持続的なキャッシュ創出を担う経営体制が必要とされていた。
河野栄子氏は1969年入社以来、営業畑で実績を積み上げ、副社長として事業統括を担当していた。従来のテレアポ中心の営業に代えて飛び込み営業を確立し、競合情報を活用した提案型営業で成果を上げてきた。1991年頃から次期社長候補と目され、内部昇格による継承が現実味を帯びていた。
決断:河野栄子氏の社長就任
1997年6月、河野栄子氏が社長に就任した。リクルート初の女性社長として注目を集めるとともに、実力主義を体現する象徴的な人事であった。副社長として本業の収益管理を担い、営業利益率約30%を確保した実績が評価された結果であった。
就任後も方針は一貫しており、まずは本業収益の最大化と債務圧縮を優先した。情報誌や人材関連事業で高収益を維持し、借入金の返済原資を確保する経営を継続した。一方で、インターネットの普及期にあっても大規模な新規投資には慎重であり、既存事業のネット化にとどまる戦略が選択された。
結果:高収益維持と構造的課題
1997年から2003年までの在任期間に、リクルートは本業の高収益体質を維持し、有利子負債の圧縮を進展させた。財務体質の改善は着実に進み、再建路線は一定の成果を上げた。安定的なキャッシュ創出企業としての基盤は、この時期に再構築された。
その一方で、ネット関連の新規事業創出や大規模な成長投資は限定的であった。ECやIT領域では先行企業が台頭し、優秀な人材が他社へ転じる動きも見られた。ただし、巨額債務という制約の下での経営であった点を踏まえると、河野体制は再建期の経営として機能したと位置付けられる。
1997年から2003年の河野体制は、営業利益率約30%を確保しつつ有利子負債を圧縮するという財務再建期の経営であった。テレアポから飛び込み営業へ転換し、提案型営業を定着させた営業改革の実績が就任の背景にある。在任中にネット関連の大型投資は限定的にとどまり、ECやIT領域で先行企業に差をつけられた面はあるが、1.4兆円の債務を抱えた状況下では新規投資に回す資金余力自体が乏しかった。
「リクルートスタッフィング」を発足
1987年にシーズスタッフとして参入した派遣事業は、1999年の商号変更でリクルートブランドと統一し、地方買収を通じて全国約40拠点体制を構築した。2009年3月期には単体売上高1700億円規模に達したが、リーマンショック後の2011年3月期には1272億円へ急落した。情報誌事業と異なり、派遣は景気変動の影響を直接受ける構造であり、高成長と高ボラティリティが表裏一体の事業であった。
背景:派遣規制緩和と市場拡大
1987年、リクルートは子会社シーズスタッフを設立し人材派遣業に参入した。当初は業種が限定され、市場規模も小さかったが、1990年代後半に入り規制緩和の流れが加速する。特に製造業派遣の解禁は、企業の固定費圧縮ニーズと合致し、市場拡大が確実視される局面を迎えた。
バブル崩壊後の企業は雇用を抑制しつつ人材を確保する手段を模索していた。こうした環境変化を受け、派遣は構造的成長市場へ転換するとの見通しが広がる。リクルートにとっても、情報誌中心の収益構造を補完する新たな柱として、人材派遣の位置づけが高まっていった。
決断:商号変更と積極投資
1999年7月、子会社の商号を「リクルートスタッフィング」に変更し、派遣事業を本格成長領域として位置づけた。ブランドを親会社と統一することで信用力を高め、市場拡大局面で一気にシェア獲得を狙う戦略を採った。
さらに地方展開を強化するため、有力派遣会社の買収を推進。2004年のオリファ買収を皮切りに拠点網を拡大し、全国約40拠点体制を構築した。専門特化ではなく幅広い業種を対象とする全方位型モデルを採用し、量的拡大による成長を志向した。
結果:成長牽引も競争激化
その結果、2009年3月期には単体売上高1,700億円規模に到達し、リクルート連結売上の中核事業へ成長した。規制緩和と企業の外部化需要を背景に、派遣事業は2000年代の売上成長を牽引する存在となった。
一方で、競合他社が広告投下と大量営業戦略でシェアを拡大し、業界順位は上位に食い込めなかった。さらに2008年以降の景気悪化により需要は急減し、2011年3月期には売上高が大きく落ち込んだ。成長産業である一方、景気変動の影響を強く受ける構造も明確となった。
1987年にシーズスタッフとして参入した派遣事業は、1999年の商号変更でリクルートブランドと統一し、地方買収を通じて全国約40拠点体制を構築した。2009年3月期には単体売上高1700億円規模に達したが、リーマンショック後の2011年3月期には1272億円へ急落した。情報誌事業と異なり、派遣は景気変動の影響を直接受ける構造であり、高成長と高ボラティリティが表裏一体の事業であった。
「ホットペッパー」を創刊。狭域ビジネスに本格参入
商圏を半径約2kmに区切り、人口密度と来店動線を前提にエリア設計する手法は、就職情報誌や住宅情報とは異なる粒度の市場設計であった。2002年度に売上高147億円、2000年代後半には400億円台に到達した。1994年の「サンロクマル」で札幌のクーポン実験に成功したことが直接の起点であり、3エリアでのテスト配布を経て30エリアへ展開する段階的手法を採った。2023年に冊子配布を休止し、ホットペッパービューティーを中心としたWeb予約基盤へ移行した。
背景:地方市場攻略の模索
1990年代までのリクルートは、就職・住宅など大都市圏向け専門情報誌で成長してきた。しかし地方都市では人口規模が小さく、単一テーマの専門誌では広告需要が十分に成立しないという構造的な壁に直面していた。ローカル市場では広告主数も限られ、都市型モデルをそのまま横展開することは困難だったのである。
この課題に対し、1994年に生活総合誌「サンロクマル」を創刊し、地域密着型の情報提供を開始した。特に札幌エリアではクーポンを前面に打ち出した構成が奏功し、飲食や美容など来店型店舗の広告需要を掘り起こすことに成功した。この実験を通じて、狭い商圏に特化した無料クーポン媒体という新たな可能性が社内で明確になった。
決断:クーポン特化冊子を全国展開
2000年7月、リクルートは「ホットペッパー」を試験創刊し、新潟・長岡・高松の3エリアで配布を開始した。冊子は無料とし、飲食店や美容室のクーポンを主軸とする構成を採用。商圏を半径約2km圏内に区切り、人口密度や来店動線を前提にエリア設計を行うことで、広告効果を最大化するモデルを構築した。
テスト結果を踏まえ、2001年には30エリアへ拡大し、本格的な全国展開に踏み切った。地方都市では既存の広告会社と提携し、地域営業網を活用して迅速に広告主を開拓した。こうして「狭域×無料×クーポン」という明確なポジショニングを持つ媒体として、ホットペッパーは成長軌道に乗った。
結果:紙から予約基盤への転換
2002年度には売上高147億円を達成し、2000年代後半には売上高400億円台へ拡大。無料クーポン冊子として地域の来店型ビジネスの集客基盤となり、狭域広告モデルを確立した。一方で同業他社の参入やリーマンショックによる広告市況悪化により、成長は次第に鈍化した。
その後、ホットペッパービューティーを中心にオンライン予約機能を強化し、紙媒体からWebプラットフォームへ軸足を移行した。クーポン冊子としての役割は縮小し、2023年には冊子配布を休止。ホットペッパーは、紙の地域媒体からデジタル予約基盤へと事業構造を転換することになった。
商圏を半径約2kmに区切り、人口密度と来店動線を前提にエリア設計する手法は、就職情報誌や住宅情報とは異なる粒度の市場設計であった。2002年度に売上高147億円、2000年代後半には400億円台に到達した。1994年の「サンロクマル」で札幌のクーポン実験に成功したことが直接の起点であり、3エリアでのテスト配布を経て30エリアへ展開する段階的手法を採った。2023年に冊子配布を休止し、ホットペッパービューティーを中心としたWeb予約基盤へ移行した。
フリーマガジン「R25」を創刊
20万部のプレ創刊から4ヶ月で50万部に拡大し、最盛期には60万部に達した。しかし広告主は大企業中心の高単価モデルであり、電通との合弁で営業力を補完してもコミッション負担が収益を圧迫した。スマートフォンの普及で通勤時間の情報接触が紙からデジタルへ移行し、2015年に紙を休止、2017年にサイバーエージェントへ事業売却された。紙の無料誌モデルが成立する時間軸は約10年であった。
背景:男性向け無料誌の構想
2004年、リクルートは社内新規事業制度を通じて、25歳以上の都心勤務男性を対象とした無料情報誌「R25」を企画した。ホットペッパーが女性向け生活情報で成功していた一方、男性ビジネス層に特化した無料媒体は未成熟であり、広告市場の新領域を開拓できる余地があると判断したためである。誌面は編集記事を厚くし、読み物としての価値を高める設計とした。
当時は紙媒体広告が依然として有効であり、都市部の通勤導線を押さえれば大量接触が可能であった。そこで、駅ラックを中心とする配布モデルを前提に、一定規模以上でなければ広告媒体として成立しないとの認識のもと、創刊段階から大規模発行を志向した。
決断:創刊直後から50万部へ拡大
2004年3月、R25は都内中心に20万部でプレ創刊された。そしてわずか4か月後の同年7月には、首都圏全域で50万部体制へ拡大する決断を下した。段階的検証ではなく、初期段階から規模を取りにいく判断であり、広告主に対して“都市型大規模媒体”としての存在感を示す狙いがあった。
配布場所は主要駅の通勤動線を中心に確保し、働く男性への高頻度接触を実現した。無料かつ高品質な誌面設計により発行部数は一時60万部規模まで拡大し、首都圏ビジネス層向け媒体として一定の認知を獲得した。
結果:紙モデルの限界と売却
しかし広告主は大企業中心であり、高単価モデルの維持は容易ではなかった。2005年には電通と合弁でMedia Shakersを設立し営業力を補完したが、コミッション負担が収益を圧迫した。加えてスマートフォンの普及により、通勤時間の情報接触は紙からデジタルへ急速に移行した。
2014年に発行部数を縮小、2015年に紙媒体を休止しWebへ転換したものの、競争は激化していた。最終的に2017年、R25事業はサイバーエージェントへ売却され、紙無料誌モデルではなく、1つのブランドとして継承されることになった。
20万部のプレ創刊から4ヶ月で50万部に拡大し、最盛期には60万部に達した。しかし広告主は大企業中心の高単価モデルであり、電通との合弁で営業力を補完してもコミッション負担が収益を圧迫した。スマートフォンの普及で通勤時間の情報接触が紙からデジタルへ移行し、2015年に紙を休止、2017年にサイバーエージェントへ事業売却された。紙の無料誌モデルが成立する時間軸は約10年であった。
リクルートコスモスを売却
1974年の参入から31年を経て、リクルートはリクルートコスモスの株式をユニゾン・キャピタルに譲渡した。売却後、コスモスイニシアに商号変更した同社は2009年に451億円の債務超過でADRを申請した。仮にリクルートが保有を継続していれば、再び巨額の損失を引き受ける事態に陥っていた可能性が高い。2005年時点での売却は結果的にリスク遮断として機能し、リクルートが「情報・人材」に経営資源を集中する前提条件を整えた。
背景:不動産事業整理の最終局面
1970年代に参入した不動産事業は、子会社リクルートコスモスを通じて急拡大し、1980年代後半には売上高で本体を上回る規模に成長した。しかし、バブル崩壊後は土地価格の下落により巨額の含み損が顕在化し、リクルート本体が約3500億円規模の不動産を引き取るなど財務負担を背負う構造となった。
1990年代を通じて有利子負債1.4兆円の返済を進める中で、グループ再建の柱は「事業の選択と集中」に置かれ、不動産は明確にノンコア事業と位置付けられていた。財務の健全化に一定の目処が立った段階で、資本関係の整理は避けられない経営課題となっていた。
決断:ユニゾンへ経営権移行
2005年5月、リクルートはリクルートコスモス株式を投資ファンドのユニゾン・キャピタルへ譲渡し、経営権を移行することを決定した。これは単なる持株売却ではなく、バブル期の拡張戦略の象徴であった不動産事業からの完全撤退を意味した。
売却はMBOを軸とし、コスモス側の自立経営を前提に実行された。リクルートは「HR・情報」領域に経営資源を集中する方針を明確化し、資本構造を軽量化する選択を取った。創業期以来続いた不動産との資本的結びつきは、この決断により終止符を打つこととなった。
結果:後年の市況悪化を回避
売却後、リクルートコスモスは商号をコスモスイニシアに変更し上場を維持したが、2008年のリーマンショックにより業績が急悪化し、2009年には451億円の債務超過に陥りADRを申請する事態となった。
結果として、2005年時点での売却はリクルートにとって財務リスクの遮断という意味を持った。もし保有を継続していれば、再び巨額損失を抱える可能性が高かった。1970年代から続いた不動産事業はここで実質的に清算され、リクルートは情報・人材企業への回帰を確定させた。
1974年の参入から31年を経て、リクルートはリクルートコスモスの株式をユニゾン・キャピタルに譲渡した。売却後、コスモスイニシアに商号変更した同社は2009年に451億円の債務超過でADRを申請した。仮にリクルートが保有を継続していれば、再び巨額の損失を引き受ける事態に陥っていた可能性が高い。2005年時点での売却は結果的にリスク遮断として機能し、リクルートが「情報・人材」に経営資源を集中する前提条件を整えた。
当社は、リクルートコスモス設立以来、筆頭株主として資本関係を継続してまいりました。平成初頭のバブル崩壊時には、約3,500億円に上るリクルートコスモス関連不動産を取得し、同社の再建計画の実現に協力いたしましたが、その後は、大株主としての立場で互いの独自性を尊重し、それぞれの事業推進に取り組んでおります。
一方当社は、当社グループの再建計画を実行すべく、「事業の選択と集中」を経営方針に掲げ、従来からの主力事業であります人材関連事業、及び情報サービス事業への経営資源の集中を進め、ノンコア事業からの撤退、売却を行ってまいりました。このグループ再建計画も概ね最終局面を迎えつつある現状において、改めてリクルートコスモスグループとの資本関係についても見直す中、ユニゾン及びリクルートコスモスとの間で有意義な合意を得たため、ここにリクルートコスモスの経営権をユニゾンに移行することを決定いたしました。
スタッフサービスHDを買収
派遣市場で5位前後にとどまっていたリクルートが、非上場の首位スタッフサービスHDを一括取得することで順位を逆転させた。派遣業は登録スタッフ数と取引社数が競争力を左右するため、自前成長では追いつけない差を買収で埋める判断だった。しかし2008年のリーマンショックで派遣需要が急減し、従業員6000名削減を余儀なくされた。買収のタイミングとしては最悪だったが、規模統合による基盤は残り、中長期的にはHR事業の中核を形成した。
背景:派遣市場拡大と劣位
1987年の参入以降、リクルートは子会社リクルートスタッフィングを通じて人材派遣事業を拡大し、2000年代半ばには売上高1500億円規模へ到達していた。規制緩和と企業の固定費削減需要を背景に市場は急拡大し、派遣は同社の中核事業の一つへと成長していた。
しかし、業界内の順位は5位前後にとどまり、首位企業との差は埋まらなかった。特にスタッフサービスHDは、非上場ながら積極的な営業と大量動員型モデルで規模を拡大し、売上規模で先行していた。単独での成長のみで首位を狙うには時間を要する状況にあった。
決断:首位企業の一括取得
こうした状況を受け、2007年12月にリクルートは業界1位のスタッフサービスHDを買収する決断を下した。既存のリクルートスタッフィングと合わせることで、規模・拠点網・顧客基盤を同時に拡充し、派遣市場における競争地位を一気に引き上げる狙いであった。
自前主義ではなく、外部企業の取得によって順位を逆転させる戦略である。派遣業は登録スタッフ数と取引社数の量的確保が競争力を左右する市場であり、首位企業の買収は時間を買う施策でもあった。情報誌中心の企業像から総合人材企業への転換を明確にする一手となった。
結果:環境急変と統合課題
しかし、買収直後の2008年にリーマンショックが発生し、企業の雇用抑制が急速に進んだ。国内では派遣契約の終了が相次ぎ、派遣各社の業績は大きく悪化した。リクルートの派遣2社においても売上減少が顕在化し、拡大前提で描いた成長シナリオは修正を迫られた。
結果として、人員削減や拠点見直しなどの体制再構築を進めることとなり、買収は前途多難なスタートとなった。ただし、規模統合による基盤強化は残り、長期的には人材事業をグループの中核へ押し上げる契機ともなった。
派遣市場で5位前後にとどまっていたリクルートが、非上場の首位スタッフサービスHDを一括取得することで順位を逆転させた。派遣業は登録スタッフ数と取引社数が競争力を左右するため、自前成長では追いつけない差を買収で埋める判断だった。しかし2008年のリーマンショックで派遣需要が急減し、従業員6000名削減を余儀なくされた。買収のタイミングとしては最悪だったが、規模統合による基盤は残り、中長期的にはHR事業の中核を形成した。
Indeedを買収
Indeed買収の起点は、トップダウンの戦略ではなく、当時36歳の出木場久征氏の提案であった。従業員550名・赤字のテクノロジー企業に1000億円超を投じる判断は、安定収益の派遣会社買収案と比較され社内で議論が分かれた。DDは数週間〜1ヶ月の短期間。買収後は提案者自身がIndeedのCEOに就任し、現地に裁量を委ねるPMIを実行した。FY2022にはHRテクノロジー事業で当期利益13億ドルを計上し、リクルートの収益構造を根本から転換した。
背景:HR世界首位への転換
2012年に峰岸真澄氏がリクルートHDのCEOに就任し、「HR分野でグローバルのトップになる」という明確な目標を掲げた。これにより経営の重心は国内情報誌中心から海外展開へと移行し、成長の主戦場は北米・欧州へと再定義された。グローバルで競争するには、既存事業の延長ではなく、規模と技術の両面で飛躍が必要と認識された。
背景には、2000年代の中国単独進出での苦戦があった。現地組織の統治や人材マネジメントで躓き、自前主義による海外展開の限界が露呈した。この反省から、海外は買収を通じて参入する方針へ転換し、まずは小規模案件を重ねてPMIの型を蓄積する戦略を採った。
2010年前後は海外派遣会社の買収が中心で、テクノロジー企業を主軸に据える構想は明確ではなかった。HRで世界首位を目指すとしても、派遣で規模を積み上げるのか、デジタル領域へ踏み出すのかは定まっていなかった。そうした揺らぎの中で、大型買収を実行できる資金枠を確保し、次の一手を探る局面にあった。
決断:Indeedを十億ドル取得
買収候補にIndeedが浮上した契機は、当時36歳で新規事業を担っていた出木場久征氏の提案であった。米国発の求人検索エンジンであるIndeedは、日本では無名に近い存在だったが、創業者と事業モデルに将来性を見出し、社内で買収を強く推した。トップ主導ではなく、個人の熱量が端緒となった案件である。
Indeedは2004年創業、従業員約550名、売上は100〜200億円規模と推定される一方、広告投資と開発費で赤字を計上していた。買収価格は約10億ドル、当時のリクルートにとっては1000億円超の初の巨額案件である。安定収益の派遣企業買収案と比較され、社内では議論が分かれた。
数週間から1か月という短期間のDDを経て、峰岸社長はIndeed買収を決断した。失敗すれば経営責任を問われかねない規模であったが、テクノロジーがHRの構造を変えるとの前提に賭けた判断であった。買収後は出木場氏がIndeedのCEOに就任し、現地に権限を委ねる体制を敷いた。
結果:テック企業への転身
買収後、Indeedは検索型求人というモデルを軸に北米・欧州で拡大を続け、2010年代を通じてグループの成長を牽引した。HRテクノロジー領域の売上は拡大し、リクルートの収益構造は紙媒体中心からオンライン中心へと転換していった。事業ポートフォリオの軸が明確に変わった。
財務面では、買収に伴い無形固定資産が大幅に計上され、資本政策の見直しも進んだ。成長資金の確保と透明性向上を目的に、2014年には東証一部へ上場するに至る。Indeedの存在は、上場ストーリーの中核的資産として位置付けられた。
PMIでは統合を急がず、Indeedの経営陣とエンジニア組織に裁量を委ねる方針を採った。現地主導の意思決定と技術重視の文化が維持され、事業は持続的に成長した。結果として、リクルートは総合HR企業からHRテクノロジー企業へと自己定義を変え、市場からの評価も大きく変化した。
Indeed買収の起点は、トップダウンの戦略ではなく、当時36歳の出木場久征氏の提案であった。従業員550名・赤字のテクノロジー企業に1000億円超を投じる判断は、安定収益の派遣会社買収案と比較され社内で議論が分かれた。DDは数週間〜1ヶ月の短期間。買収後は提案者自身がIndeedのCEOに就任し、現地に裁量を委ねるPMIを実行した。FY2022にはHRテクノロジー事業で当期利益13億ドルを計上し、リクルートの収益構造を根本から転換した。
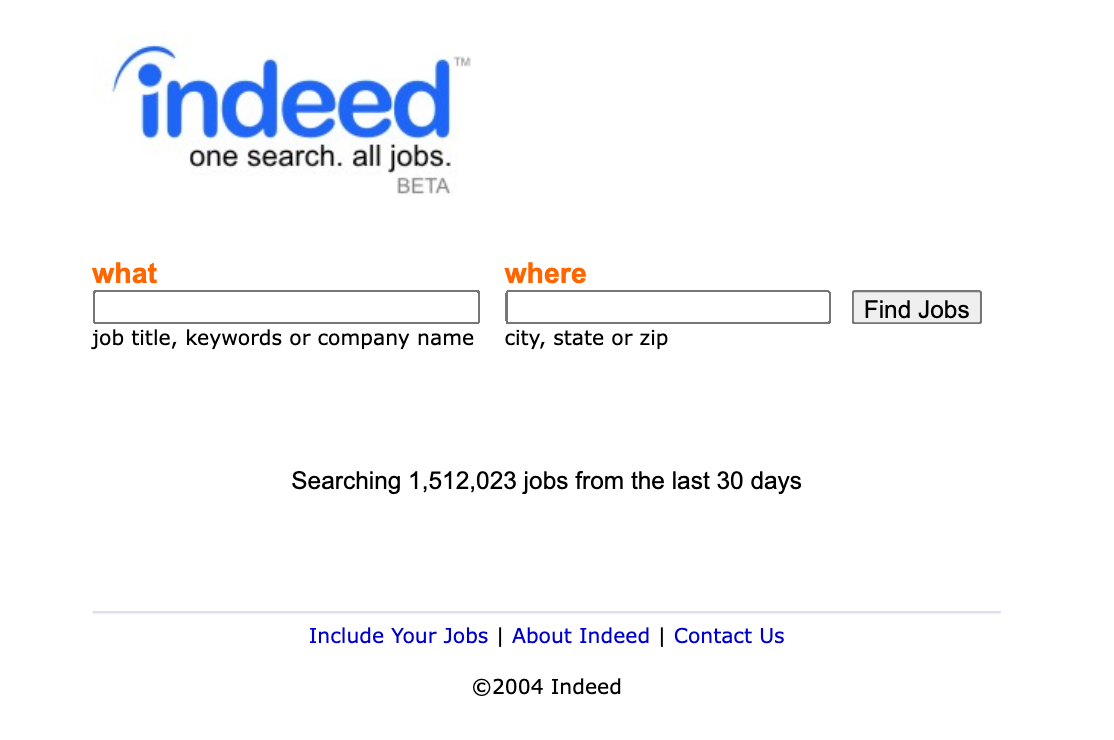
2012年に社長になったのですが、最初のアジェンダというのは、グローバルか国内かという選択でした。もともとは国内の人材派遣会社、今でいうメディア&ソリューションが基盤だったんですよ。海外の売上比率は3.7%くらいしかなかった。
国内では主要な領域は全てナンバーワンのポジションでしたから、もっと強いナンバーワンになるのか、それとも海外に打って出るのかというクリティカルな論点でした。社長就任前の10年ごろからこの議論はしていたのですが、どうせ海外に出るんだったら中途半端にではなく、われわれのオリジンである人材ビジネスの世界ナンバーワンになるぞと決めました。
自前で進出するかM&A(企業の合併・買収)をするかについては、2000年初頭に中国に進出したときの反省がありました。商習慣も分からないし、日本のビジネスモデルとマネジメントをそのまま持っていってもうまくいかなかった。ですので、M&Aにしました。(略)
(注:Indeedが買収候補に上がったときは)「何だ、その会社は」と(笑)。まだあまり知られていない会社だったので。当時、われわれは「人材ビジネスのナンバーワン企業になる」とアナウンスしていたので、世界中の人材ビジネスのプレーヤーを探して交渉していたのですが、そのときに数社あった候補のうちの一社でした。
実はその数社の中には、古いビジネスモデルだけれども、うちが買収すれば間接コストの削減や、削減による相当なリターンを得られるという会社もありました。その会社はIndeedよりもっと安かった。Indeedは04年に創業して、何十億円も赤字を出していた時期があったのに1000億円という買収金額でしたからね(笑)。
もう“恋”みたいなものでしたよね。いろいろ話しているうちに、創業者が大好きになった。この人、いいな。いいこと考えてる。この人と仕事がしたい。買収するときには、会社から“経済性とかなんとか”と、いろいろ言われるんですが……(笑)。
でも、効率的に採用ができる、ということは、確実に社会の効率を上げるわけです。人を採用したい、と考えたら、あっという間に応募が来て、すぐ今日にでも採用に至れる。仕事を探している人は、あっという間に理想の会社が探せる。そんなことができたら、最高じゃないですか。だから、僕らはそんな世界を目指して突き進むわけです
一度交渉して日本に持ち帰り、戻ってきて答えが変わっていたら相手に見透かされます。「俺がリーダーなんだ」と認識させることで、買収後の運営もやりやすくなりました。今思えば、よく会社は私にすべてを任せたなと思います。ちょうど峰岸が社長になって初めての買収だったこともあり、「これが失敗したらあなたの求心力に関わりますよ」と苦言を呈する取締役もいたと聞いています。そのとき峰岸は「出木場が問題ないと言っています」と堂々と言い放った。これは私の中でも「ちゃんとやらなきゃ」という思いが強くなります。そして、あと5年は会社を辞められなくなったなと思いました(笑)。
スタディサプリのSaaS化
買い切り5000円から月額980円への価格転換は、単価を5分の1以下にする代わりに会員数で損益分岐を超える賭けであった。2016年3月末に有料会員16.7万人で黒字化し、コロナ禍の2021年には157万人に到達した。山口文洋氏が「ネットサービスとして許容できる金額は980円」と判断した点が転換の核心であり、予備校型の高単価モデルとは正反対の設計思想で教育市場に参入した。
背景:新規事業発の教育挑戦
受験サプリは、リクルートの新規事業コンテストを契機に山口文洋氏らが構想した高校生向け学習アプリである。発案者を巡る言及が複線化する点は同社の新規事業文化を象徴する。開発は土井浩司氏を中心に10名規模で開始され、短期間で数十名体制へ拡大した。スマホ黎明期において内製志向でプロダクトを磨いた。
最大の課題は人気予備校講師の確保であった。実績の乏しい新サービスに講義動画を提供する動機は弱かったが、肘井学氏らへの直接交渉を通じて英語・数学の講師を確保し、2014年までに約1000時間の動画を蓄積した。当初は1講座5000円の買い切り型で提供したが、価格の高さが普及の障壁となった。
決断:月額980円SaaSへ転換
普及を優先し、1講座5000円の買い切り型から月額980円のSaaS型へと大幅に転換した。単価を下げる代わりに大量会員の獲得を前提とし、継続課金でLTVを積み上げる設計へ変更した。損益分岐には数十万規模の会員が必要であり、価格・体験・獲得の三位一体で再設計が求められた。
同時に2012年からテレビCMを投下し、短期で認知拡大を図った。広告評価は分かれたが、月額モデルの成立には初速の会員基盤が不可欠であった。教材販売から継続サービスへと位置付けを改め、講師動画という重い原価資産をスケールで回収する構造へ移行した。
結果:会員増と黒字化の実現
月額化により有料会員が増加し、2016年3月末に16.7万人へ到達、黒字化を達成した。高単価モデルの壁を越え、継続価値を前提とした教育サービスとして定着が進んだ。コンテンツ追加が会員維持を後押しし、規模拡大の循環が形成された。
2020年以降のコロナ禍でオンライン学習需要が急増し、会員数はFY2020の79.9万人からFY2021の157万人へと約2倍に拡大した。外部環境の変化を追い風に、低単価継続課金モデルが確立され、教育SaaSとしての基盤を固めた。
買い切り5000円から月額980円への価格転換は、単価を5分の1以下にする代わりに会員数で損益分岐を超える賭けであった。2016年3月末に有料会員16.7万人で黒字化し、コロナ禍の2021年には157万人に到達した。山口文洋氏が「ネットサービスとして許容できる金額は980円」と判断した点が転換の核心であり、予備校型の高単価モデルとは正反対の設計思想で教育市場に参入した。
実は元々、受験サプリの原型というのは現在の有料モデルではありませんでした。無料の受験コンテンツを高校生に提供すれば、それを利用する子供達の会員データベースができる。それに対して例えば早稲田大学が、東京大学を第一志望にしている高校生に広告を送る。こうした、リクルートでは一般的なマッチングと広告のモデルを想定していました。
ただ、色々考えていくうちに、単に無料の模擬試験や過去問題を提供して広告で少し収益を上げたとしても、それで世の中は変えていけないな、と思いついたんです。子供達が自己実現するための大学の合格に向けて、一番近道になる勉強をする。それに必要なのはやはり、予備校での授業や通信教育などのしっかりしたコンテンツではないかと。
でも、一方でこうした予備校などは、非常に良いものですが利用するためにかなりお金がかかります。それならば、我々のサービスでは、最低限のお金はいただきつつ、質の高い授業を提供しようと。幸い、今ではスマートフォンをはじめスマートデバイスが普及している。それをターゲットにすれば、広がっていくのではないかという読みがありました。
そこで改めて考えたことが、やはりこれは、あくまでインターネットサービスの1つなんだということですね。動画視聴のサービスであれば、月額5000円なんて設定はまずありえない。消費者の立場から、ネットサービスとして許容できる金額設定はどこか。それが980円という、適度でありつつ教育格差の解消も可能な金額設定だろうと考えました。
この場合、やはり何十万人という会員規模にならなければ、損益分岐点を超えていくことはできない。長期的な視点で投資もオペレーションも大変ですが、最初にそれを進めれば競合は真似できない。高単価で限られた世帯を相手にした「縦」のサービスではなく、「横」に広がった事業設計でなければならない。こうした分析はものすごくやりました。
東京証券取引所第1部に株式上場
長らく非上場であったが、海外展開のための資金調達のために株式上場を決定。上場時の時価総額は1.7兆円で、上場に伴って2138億円を資金調達
USG Peopleを買収
オランダ(欧州)の人材派遣会社USG Peopleの株式100%を1811億円で買収することを決定。リクルートHDではFY2020の経営目標として「人材領域におけるグローバルNo.1企業となること」を掲げており、買収に踏み切った。
GlassDoorを買収
求人企業のレビューサービスを展開する米国企業Glass Doorの買収を決定。リクルートが運営するIndeedの求人検索と相乗効果が高いと判断し、買収に踏み切った。
過去最高益を達成
FY2021にリクルートHDは当期利益2977億円(前年同1316億円)を計上し、過去最高益を達成した。Indeedを中心とするHRテクノロジー事業が収益貢献した一方、派遣事業は相対的に低収益へ。