サイバーエージェントを設立
1998年に藤田晋氏が新卒入社して勤務していた人材会社インテリジェンスを退職。同年3月18日東京都港区にてサイバーエージェントを株式会社として設立した。藤田晋氏は、インターネット業界において「営業ができる会社」が少ないことを着目し、技術力のある会社が提供する商品の営業を引き受ける「営業代行」のビジネスを開始した。
まずは、インタリジェンス時代に「採用のネット媒体の営業」で成果を出していたことを実績として掲げて、まずは決済代行であるWebmoneyの営業代行の契約を締結した。
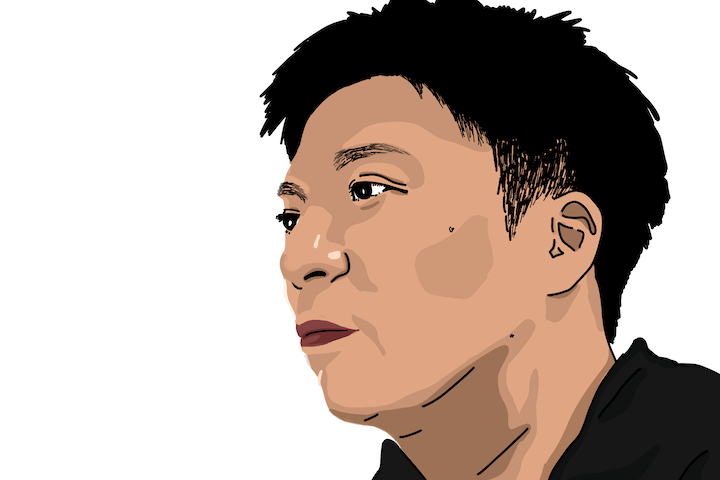
渋谷マークシティに本社移転
黒字転換(投資有価証券の売却寄与)
サイバーエージェントは黒字確保のために、保有していた投資有価証券(ベンチャー投資先企業)の売却を開始。2004年度にトラフィックゲート、GOCOO、クレッシェンドの3社、2005年度にクレッシェンド、ジェット証券の2社の株式を売却し、合計48億円の売却益を計上した。
投資育成事業を開始
アメーバピグの提供を開始
Ameba事業が黒字転換
スマホ向け大規模プロモーションを実施
Ameba事業の構造改革を実施
収益性の低いサービスの中止を決定。Ameba事業の担当従業員数を1600名から800名へと半減。収益改善を目論む
セルビアに資本参加。Jリーグクラブ経営に参入
WinTicketを設立
Abema Towersに本社移転
藤田社長の選任賛成比が低下
2019年12月の株主総会において、藤田社長の選任賛成比率が57.56%となり社長解任の危機に陥った。機関投資家がサイバーエージェントの社外取締役比率の低さを問題視し、議決権行使助言会社のISSが議案に反対したことが要因
最高益を達成
連結決算において売上高6664億円・営業利益1043億円を達成。ゲーム事業のウマ娘のヒットにより大幅増益。
一方、単体決算において、債務超過に陥っている子会社AbemaTVに対する貸付金に関して900億円の引当金を計上。このため単体ベースでサイバーエージェントは690億円の最終赤字に転落
AbemaTVへの投資を継続
FIFAワールドカップの国内放映権を取得
ウマ娘のヒットを受けて、ワールドカップの放映権を取得。AbemaTVにおける投資のため、サイバーエージェントの負担金額は不明
サクセッションプランを公表
藤田社長の候補候補について、社内から抜擢する方針を表明。取締役会を中心にサクセッションプランを始動した
企業買収を積極化
業績予想を下方修正
2023年7月にFY2023(9月期)の下方修正を発表。ウマ娘のヒットの反動により75%の経常利益の減益を予想