初代塩野義三郎薬種問屋を創業
明治11年に初代塩野義三郎氏は、和漢薬を販売するための薬酒問屋を大阪東区道修町にて創業した。当時は個人商店としての運営であり、大阪で薬問屋が集積する道修町において販売業に従事した。
創業期における転機は、明治30年後から外国商社と直接取引を実施し、欧米から洋薬の輸入を開始したことに始まる。その後、輸入にとどまらず、医薬研究を行うために「研究所」を新設することで「輸入問屋」に加えて「医薬品メーカー」の事業展開を志向した。
ただし、第一次世界大戦(1914年〜1919年)までは輸入品への依存度が高く、塩野義としては「問屋」が事業の主力であった。
塩野義製薬株式会社に商号変更
塩野義化学を合併・赤穂工場を発足
東京証券取引所に株式上場
総合ビタミン剤「ポポンS」を発売
サルファ剤「シノミン」を発売
中央研究所を新設・抗生物質の開発を本格化
摂津工場を新設
抗生物質「シオマリン」を発売
金ケ崎工場を新設
抗生物質「フルマリン」を発売
第1次中期経営計画を開始
非注力事業の売却(植物薬品・臨床検査・動物薬・工業薬品)
医療卸オオモリ薬品とスズケンが合併(卸撤退)
高血圧症治療薬「クレストール」を発売
サイエルファーマを買収
Viiv社からロイヤリティー収入を確保
ViiV社について
2001年に塩野義製薬はGSK社と合弁会社を設立して「インテグレース阻害剤」の共同研究を開始した。ところが、HIV市場に着目したファイザー社が、GSKと共同でViiV社を設立し、HIV領域の創薬事業はViiV社に移転された。このため、塩野義製薬としてはHIVの創薬に関して、当初はGSKと共同で行う目論見が崩れてしまった。
ViiV社との契約変更
2012年10月に塩野義製薬(手代木功・社長)は、HIVインテグレース阻害薬に関して、ViiV社(HIV関連市場において世界2位の企業)との提携の枠組みの変更を実施した。骨子は、下記3点であった。
①塩野義製薬が開発する「DTG(ドルテグラビル)に関する権利をViiV社に移転する代わりにViiV社の株式10%を保有する
②ViiV社から配当を確保しつつ取締役を1名派遣する
③DTGの販売において約10%〜約20%のロイヤリティー収入を得る
この契約により、塩野義製薬はHIV関連の医薬品について、ViiV社からロイヤリティー収入を得るとともに、ViiV社の株式を確保することによって配当を確保。この結果ViiV社の株式保有比率は「GSK76.5%・ファイザー13.5%・塩野義製薬10%」となった。
一方、塩野義製薬がHIV領域において自前でグローバル展開を行うことを諦め、全面的にViiV社に任せる方針を決定。知的所有権としての対価を得る枠組みであった。この契約の代償は、DTGの米国における販売で、塩野義製薬は自前の販路を活用することを諦める形となり、自社開発製品の米国販売は困難な状態となった。
ロイヤリティー収入の拡大
塩野義製薬にとってViiV社との契約体系の変更は代償を伴うものであったが、ViiV社におけるHIV領域の創薬は順調に進展。2010年代から2020年代を通じて、塩野義製薬は莫大なロイヤリティー(年間約2000億円)収入を確保するに至った。
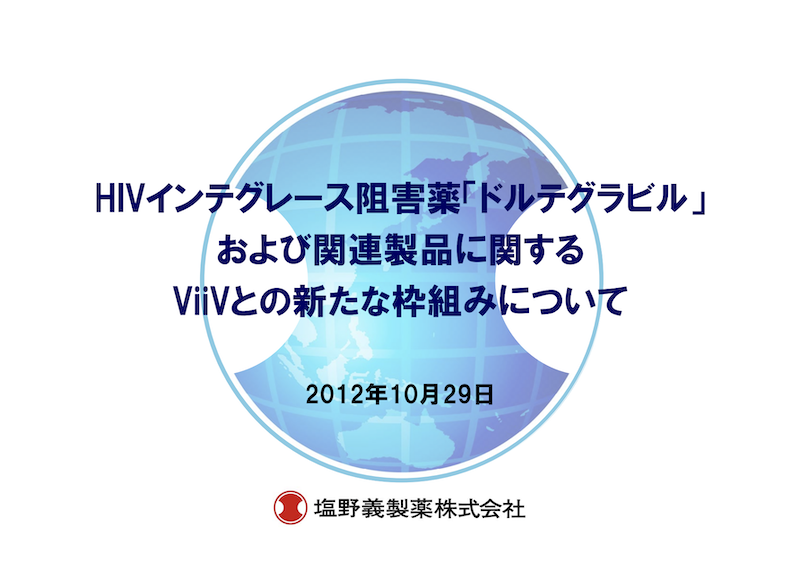
中期経営計画「Shionogi Growth Strategy 2020」を開始
HIV感染症治療薬「デビケイ」を発売
中期経営計画「Shionogi Growth Strategy 2030」を開始
過去最高益・希望退職者を募集
ViiV社からのHIV関連のロイヤリティー収入が好調に推移し、2023年3月期に塩野義製薬(手代木功・社長)は、当期利益1849億円を計上して過去最高益を達成した。
しかし、国内における医薬品販売は低迷し、Covid19の流行に伴う感染症治療薬の特需も一巡したことで、人員余剰が顕在化した。そこで、塩野義製薬は国内における希望退職者の募集を決定して「特別早期退職プログラム」を実施。200名の募集に対して301名が退職に応じた。